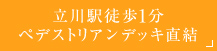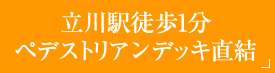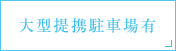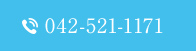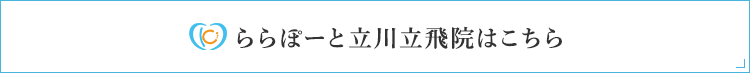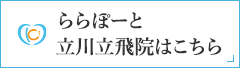こんにちは☀️
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
「なんとなく胃の調子が悪い」「胃が重い…でも病院に行くほどじゃないかも?」そんな方へ
「最近、胃がすっきりしない」
「食後にお腹が張る感じが続いている」
「健康診断で『慢性胃炎』と言われたけど、どうすればいいか分からない…」
このような経験、ございませんか?💦
実は、これらの症状や診断の裏にあるのが、「慢性胃炎」という病気です。
名前だけは聞いたことがある方も多いと思いますが、詳しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
日々多くの患者さまを診ていると、「症状が軽いから放っていた」「健診で見つかってびっくりした」「ピロリ菌って何?」という声を本当によくお聞きします👂
慢性胃炎は、初期にはほとんど自覚症状がないことが多く、見逃されやすい病気です。
しかし、放置してしまうと胃の粘膜が少しずつ傷んでいき、将来的に胃がんのリスクが高まることもあります⚠
中には、「もっと早く調べておけばよかった…」という方も少なくありません。
この記事を通して、ご自身の胃の健康について、ちょっと立ち止まって考えるきっかけになれば幸いです☺️
本日のブログでは、こんな疑問にお答えします!
1️⃣慢性胃炎ってどんな病気?
2️⃣ピロリ菌との深い関係
3️⃣萎縮性胃炎と腸上皮化生の意味
4️⃣「無症状」であることの怖さ
5️⃣診断の決め手は内視鏡検査
6️⃣治療の本質は「原因の除去+胃粘膜の保護」
7️⃣自己免疫性胃炎というもう一つの原因
8️⃣最後に~胃の健康を守るために今できること~
など、専門的な内容も丁寧に解説していきます♪
🔸1. 慢性胃炎ってどんな病気?
慢性胃炎とは、「胃粘膜に長期間持続する炎症がある状態」を指します。
これは単なる「胃の不調」ではありません⚠️
問題の核心は、「胃粘膜の構造そのものが変化していく」という点です。
🔸胃粘膜の変化には段階がある?
慢性胃炎は以下のような流れで進行することがあります。
- びまん性発赤(軽い炎症)
- 表層性胃炎(浅い炎症が広がる)
- 萎縮性胃炎(胃粘膜の萎縮が始まる)
- 腸上皮化生(胃粘膜が腸の細胞に似た形に変化)
- 異型上皮・発がん
胃の粘膜が薄くなり、腸のような細胞に変わると、胃の本来の防御機能が低下し、胃がんのリスクが高まります。
胃カメラ(内視鏡)で偶然見つかることも多く、「無症状=問題なし」とは限りません。
実際、症状が軽くても、胃の粘膜が大きく萎縮しているケースもあります。
🔸2. ピロリ菌との深い関係
慢性胃炎の最大のリスクファクター(ある病気にかかる確率を高める要因のこと)は、ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)という細菌です🦠
🔬 ピロリ菌の特徴
・幼少期に経口感染(主に親から)
・胃酸の中でも生き延びる特殊な能力
・胃粘膜に定着し、慢性的に炎症を起こす
・数十年単位で粘膜を傷つけ続ける
ピロリ菌に感染している人の胃粘膜は、炎症・萎縮・腸上皮化生が進行しやすくなります。
日本では40歳以上の半数が感染しているとされていましたが、現在は若年層を中心に感染率は低下傾向です。
🔎 胃がんの約9割はピロリ菌感染が関係しているといわれています!
🔬 ピロリ菌とは?
|
▼ 特徴 ▼ |
▽ 内容 ▽ |
|
・大きさ |
約3μm(ミクロン) |
|
・感染部位 |
主に胃の粘膜 |
|
・感染経路 |
主に口から(経口感染) |
|
・感染の時期 |
多くは**幼少期(5歳未満)**に感染 |
|
・感染後の状態 |
自然に消えることはほぼなく、一生感染が続く |
🦠 ピロリ菌の生き残り戦略
通常、胃の中は強い酸性(pH1~2)で、ほとんどの細菌は生きられません。
しかしピロリ菌は、「ウレアーゼ」という酵素を分泌して胃酸を中和することで、生き延びることができます。
・ウレアーゼ → 尿素を分解 → アンモニアを生成 → 胃酸を中和
・胃の粘液の中に潜り込み、免疫の攻撃からも逃れる
🔍 ピロリ菌は胃の“奥の奥”に潜んで長期間炎症を引き起こす、いわば“隠れた慢性炎症の主犯”です。
📈 日本における感染率
|
▼ 年齢層 ▼ |
▽ 感染率の目安 ▽ |
|
60代以上 |
約 50% 以上 |
|
40代 |
約 30% 前後 |
|
20代以下 |
5〜10% 以下(減少傾向) |
かつては上下水道が整っていなかった時代に、家庭内で水や食事を通じて親から子へ感染するケースが多かったと考えられています。
🤒 ピロリ菌が引き起こす病気
ピロリ菌は“胃のトラブルメーカー”といっても過言ではありません。
感染により、以下のような病気のリスクが高まります。
🔹 主な関連疾患
|
▼ 病気 ▼ |
▽ 説明 ▽ |
|
慢性胃炎 |
ピロリ菌感染の最も基本的な病態。無症状でも炎症が持続。 |
|
萎縮性胃炎 |
粘膜が薄くなり、胃酸の分泌が低下。 |
|
腸上皮化生 |
胃粘膜が腸の細胞に変化。がん化のリスクが上昇。 |
|
胃潰瘍・十二指腸潰瘍 |
胃酸と炎症で粘膜に穴が開く状態。 |
|
胃がん |
日本人の胃がんの約90%がピロリ菌感染と関連。 |
|
MALTリンパ腫 |
胃のリンパ組織から発生する特殊な腫瘍。除菌で治ることも。 |
☠️ 世界保健機関(WHO)は、ピロリ菌を「発がん性微生物(グループ1)」に分類しています。
🔍 ピロリ菌の検査方法
胃カメラあり・なしの両方で検査可能です。
【胃カメラなしでできる検査】
・尿素呼気試験(UBT):最も精度が高く、除菌後の判定にも最適
・抗体検査(血液 or 尿):過去の感染を含めて陽性になる
・便中抗原検査:子どもや高齢者でも受けやすい
【胃カメラと併用する検査】
・迅速ウレアーゼ試験(RUT):胃粘膜を少し採って調べる
・組織鏡検法・培養検査:詳細に調べるときに実施
🧬 除菌するとどうなる?
・胃がんのリスクが約3分の1〜5分の1に低下
・胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発がほぼなくなる
・胃の調子がよくなる人も多い
ただし、除菌後でも「萎縮性胃炎」「腸上皮化生」が進行している場合、胃がんリスクはゼロにはなりません。
そのため、年に1回の内視鏡検査が推奨されます。
🔸 3. 萎縮性胃炎と腸上皮化生の意味
🔹萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)
胃粘膜が薄くなり、胃液(胃酸や消化酵素)を分泌する能力が低下している状態です。
これは、ピロリ菌感染が長期間続いた結果として現れます。
胃カメラで見ると、粘膜の色が白っぽくなる・血管が透けて見えるなどの変化が特徴です。
🔹腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)
胃の粘膜細胞が腸の細胞のように変化してしまった状態のことをいいます。
これ自体ががんではありませんが、発がんのリスクを高める前がん病変です。
腸上皮化生のある方には、年に1回の内視鏡検査が推奨されます👨⚕️
🔸 4. 「無症状」であることの怖さ
慢性胃炎の多くは、初期には自覚症状がありません。
「胃が痛くない=健康」と思ってしまう方が多いのですが、内視鏡で見ると進行していたというケースは非常に多いです。
たとえば…
・症状なし → 胃カメラで広範な萎縮性胃炎
・軽いもたれ感 → ピロリ菌陽性+腸上皮化生あり
🔔 慢性胃炎は、「胃がんになりやすい状態」に気づくための警告灯のような存在です。
🔸5. 診断の決め手は内視鏡検査
胃の状態を正確に診断するには、やはり胃カメラ(上部消化管内視鏡)が最も信頼できます。
🔍 胃カメラでわかること
・粘膜の色・形・厚み
・炎症の有無
・萎縮の範囲
・腸上皮化生の可能性
・がんやポリープの有無
・必要に応じて生検(組織検査)
加えて、胃カメラ中にピロリ菌の迅速検査や、特殊染色・NBI観察などを用いることで、より精密な評価が可能になります。
内視鏡専門医の役割は、「見逃さない」「早期に発見する」ことです!
🔸6. 治療の本質は「原因の除去+胃粘膜の保護」
慢性胃炎の治療は、単に「胃薬を飲んで症状を抑える」ことではありません。
🎯 本質的なアプローチとは?
1.ピロリ菌の除菌治療
・抗生剤 + 胃酸抑制剤の3剤併用療法
・1週間の内服で、約80~90%が成功します
・失敗しても、2次除菌でほぼ解決可能です◯
2. 除菌後の粘膜修復と経過観察
・除菌しても、萎縮や腸上皮化生は残ることがあります
・特に高度萎縮の方には胃がんリスクが残るため、年1回の内視鏡が重要です
3. 生活習慣の見直し
・刺激物・飲酒・喫煙を控える
・規則正しい食事と睡眠
・ストレスマネジメント
💡 除菌後に胃の調子が大きく改善する方も多いですが、粘膜ダメージの回復には時間がかかるため、焦らず長い目で見ることが大切です。
🔸7. 「自己免疫性胃炎」という、もう一つの原因
「自己免疫性胃炎」とは、どんな病気か?🤔💭
・胃の壁細胞(胃酸を出す細胞)に対して、自己免疫が働いてしまう疾患です
・ピロリ菌とは無関係に、慢性胃炎を引き起こします
・進行すると胃酸分泌が極端に低下し、消化機能や栄養吸収に影響が出ます
🔹特徴
・ビタミンB12(赤血球の生成やDNA合成、神経機能の維持に不可欠)吸収障害
→ 悪性貧血(巨赤芽球性貧血)につながる恐れ
・胃底腺ポリープ(胃の胃底腺という部分が大きくなったもの)が多発
・神経内分泌腫瘍(神経内分泌細胞から発生する腫瘍で、希少がんの1つ)のリスク
・内視鏡では胃体部を中心に強い萎縮
・橋本病、1型糖尿病など他の自己免疫疾患を合併することもあります
🩺 ポイント
・ピロリ菌が陰性でも、慢性胃炎がある場合は自己免疫性胃炎の可能性があります
・ビタミンB12欠乏症状(しびれ、疲労感、記憶力低下など)にも注意が必要です
これは定期検査による「がんや貧血の早期発見」が大切になります📢!!
8.📝 最後に 〜胃の健康を守るために、今できること〜
「慢性胃炎」と聞くと、多くの方は「ちょっとした胃の不調」「一時的な炎症」くらいに思われるかもしれません😥
実際、症状がほとんど出ないことも多く、「放っておいても大丈夫だろう」と軽く見られがちな病気です。
しかし、慢性胃炎は“今”の症状だけでなく、“未来”に起こる病気と深く関わっているということです。
今は痛みがなくても、「沈黙の胃炎」がじわじわと進行していることもあります🌀
健康診断や人間ドックで“胃炎あり”や“ピロリ菌陽性”と言われた方は、
ぜひ一度、専門医による内視鏡検査をご検討ください。
🛡️ 胃は、日々の暮らしと深くつながっています!
胃は、私たちが食べるもの・感じるストレス・飲む薬など、日々の生活にとても敏感な臓器です。
・仕事や家事、育児に追われて食事が不規則になっていませんか?🍽️
・ストレスや寝不足が続いていませんか?🛌
・胃薬や鎮痛剤を何となく長く飲み続けていませんか?💊
日々のちょっとした積み重ねが、胃にとっては大きな負担になっていることもあります。
逆に言えば、生活習慣を少し見直すことで、胃の状態を大きく改善できることもあります🙆
胃は、毎日休まず働いてくれている臓器です。
この機会に、ぜひ一度、ご自身の「胃の健康」と向き合ってみてはいかがでしょうか?
当院にも、慢性胃炎・胃痛・胃の不快感・嘔気などでお悩みの患者さまも多くいらっしゃいます。診断や定期的なフォローとして必要な内視鏡検査については、全例内視鏡専門医が施行し、麻酔(鎮静剤)も使用しながら、「痛くない・辛くない」内視鏡検査をご提供できるよう、努めております。症状が改善されない方、調子が悪くご心配の方、ご不安の方はお気軽にご相談くださいませ💁♀️