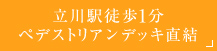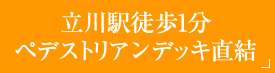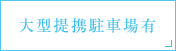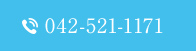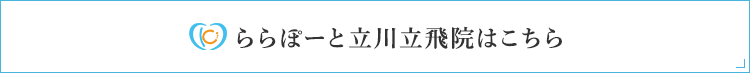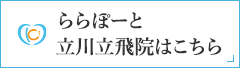こんにちは🌈
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
本日は多くの方が一度は耳にしたことのある「貧血」について、詳しく解説したいと思います❗
■ 貧血とは?
貧血とは、血液中の赤血球やヘモグロビンが基準値よりも少なくなった状態を指します。
ヘモグロビンは酸素を体の各組織に運ぶ役割を担っており、これが不足すると、全身が酸欠状態に陥り、さまざまな症状が現れます。
日本では、特に女性に多く見られ、20〜40代の女性の5人に1人が何らかの貧血を抱えているとも言われています。
■ 主な症状
貧血の症状は、軽度では気づかれにくいこともありますが、以下のようなものが代表的です。
・全身のだるさ、疲れやすさ
・めまい、立ちくらみ
・動悸(どうき)や息切れ
・顔色が青白くなる
・頭痛や集中力の低下
・爪が割れやすくなる、スプーン状になる
・舌の痛み(舌炎)や口角炎
これらの症状が長引く場合は、放置せず医療機関の受診が必要です。
■ 貧血の主な原因
貧血にはいくつかのタイプがあり、原因もさまざまです。代表的な3つを紹介します。
①鉄欠乏性貧血(もっとも多いタイプ)
原因: 鉄分の不足(偏った食生活、月経、妊娠、授乳、慢性的な出血など)
特徴: ヘモグロビンの材料である鉄が不足することで発症。特に若い女性や成長期の子ども、妊婦に多い。
②巨赤芽球性貧血(ビタミンB12や葉酸の不足)
原因: 胃の病気(萎縮性胃炎、胃の切除)や偏食、アルコール依存など
特徴: DNA合成がうまくできず、大きくて未熟な赤血球(巨赤芽球)ができる
③溶血性貧血、再生不良性貧血など
原因: 自己免疫、薬剤、骨髄の異常など多岐にわたる
特徴: 急激に悪化することがあり、専門的な検査と治療が必要
■診断と検査
貧血の診断には血液検査が欠かせません。以下のような検査項目が基本となります。
・ヘモグロビン濃度(Hb)
・赤血球数(RBC)
・ヘマトクリット(Hct)
・血清鉄・フェリチン(貯蔵鉄)
・ビタミンB12
・網状赤血球(骨髄の働きを反映)
貧血の背景に消化管出血(胃潰瘍や大腸がん)がある場合もあり、便潜血検査や内視鏡検査が行われることもあります。
■治療法
貧血の治療は、原因に応じて異なります。以下が基本的な方針です。
〜鉄欠乏性貧血の場合〜
・鉄剤の内服または点滴
・食生活の見直し(赤身肉、レバー、緑黄色野菜など)
・原因の治療(過多月経、消化管出血など)
・巨赤芽球性貧血の場合
・ビタミンB12や葉酸の補充
・胃の病気の管理
〜その他の貧血〜
溶血性: 原因除去や免疫抑制薬の使用
再生不良性: 造血幹細胞移植や免疫療法など高度な治療
■食事と生活習慣のアドバイス
日々の生活の中で貧血を予防・改善するためには、バランスのとれた食事が重要です。
鉄を多く含む食品
・赤身の肉(牛肉、豚肉など)🥩
・レバー
・魚介類(カツオ、マグロ)🐟
・大豆製品
・ほうれん草、小松菜🥬
※ビタミンCを一緒に摂ることで鉄の吸収が高まります。
また、カフェイン(お茶やコーヒー)は鉄の吸収を妨げるため、食後すぐの摂取は控えめに😢
それでは、貧血に有効な栄養素(特に鉄分・ビタミンC・葉酸・ビタミンB12など)を意識したレシピをご紹介します👨🍳
日々の食事に取り入れやすく、栄養バランスも良いレシピをいくつかピックアップしました。
🥩 レシピ①:牛肉とほうれん草のガーリックソテー(鉄分&ビタミンC)
ポイント: ヘム鉄が豊富な牛肉と、鉄分+ビタミンCが含まれるほうれん草の組み合わせ。
材料(2人分)
・牛赤身薄切り肉…150g
・ほうれん草…1束
・にんにく…1片
・オリーブオイル…大さじ1
・醤油…小さじ1
・塩・こしょう…少々
作り方
❶ほうれん草はさっと茹でて水気を切り、4〜5cmにカット。
❷にんにくはスライス、牛肉は食べやすい大きさに切る。
❸フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて中火で加熱。香りが立ったら牛肉を加える。
❹肉に火が通ったらほうれん草を加え、醤油・塩こしょうで味を調える。
🥚 レシピ②:レバーとにんじんのしぐれ煮(鉄分・葉酸)
ポイント: 鉄分が非常に豊富な鶏レバー+葉酸やβカロテンを含むにんじん。
材料(2〜3人分)
・鶏レバー…200g
・にんじん…1本
・生姜…1片
・醤油…大さじ2
・みりん…大さじ2
・酒…大さじ1
・砂糖…小さじ1
・ごま油…小さじ1
作り方
❶レバーは血抜きして下茹でする。にんじんは千切り、生姜も細切りに。
❷フライパンにごま油を熱し、生姜・にんじんを炒める。
❸レバーを加え、調味料をすべて入れて弱火で10分ほど煮る。
❹煮汁が少なくなったら完成。
🐟 レシピ③:マグロとアボカドのユッケ風(鉄分・ビタミンB12・葉酸)
ポイント: マグロのヘム鉄とビタミンB12、アボカドの葉酸+脂質で吸収アップ。
材料(2人分)
・マグロ赤身(刺身用)…150g
・アボカド…1個
・卵黄…1個
・醤油…小さじ2
・ごま油…小さじ1
・すりごま…小さじ1
・刻みねぎ・刻みのり…お好みで
作り方
❶マグロは角切り、アボカドも同様に切る。
❷ボウルにマグロ・アボカド・醤油・ごま油・すりごまを入れて軽く混ぜる。
❸皿に盛りつけ、卵黄をのせてネギやのりをトッピング。
🥬 レシピ④:小松菜とツナのサラダ(非ヘム鉄+ビタミンC)
ポイント: 野菜の鉄分とビタミンCに、ツナのたんぱく質で栄養バランス◎
材料(2人分)
・小松菜…1束
・ツナ缶(ノンオイル)…1缶
・かつお節…適量
・醤油・酢・ごま油…各小さじ1
作り方
❶小松菜は茹でて水気を切り、食べやすくカット。
❷ボウルに小松菜、ツナ(汁ごと)、調味料を加えて和える。
❸仕上げにかつお節をかけて完成。
⭐アドバイス
・動物性の鉄(ヘム鉄)は吸収率が高い(牛肉・レバー・魚)
・植物性の鉄(非ヘム鉄)はビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ
・乳製品・お茶・コーヒーは鉄の吸収を妨げるので食後すぐは避けましょう
🍱 お弁当に使える!貧血予防レシピ3選
① 牛肉とピーマンのオイスター炒め
ポイント: 牛肉でヘム鉄、ピーマンでビタミンCも同時に!
材料(2人分)
・牛こま切れ肉…100g
・ピーマン…2個(赤ピーマン混ぜると彩り◎)
・にんにく(チューブでもOK)…少々
・オイスターソース…小さじ2
・醤油…小さじ1
・ごま油…適量
作り方
❶ピーマンは細切り、牛肉は軽く塩こしょう。
❷ごま油でにんにくを炒め、牛肉を加える。
❸火が通ったらピーマンを加え、調味料で味付け。
冷めても美味しく、お弁当にぴったりです。
② 卵とツナの鉄分ふんわりオムレツ
ポイント: 卵のビタミンB12とツナの鉄分でエネルギー補給。
材料(1〜2人分)
・卵…2個
・ツナ(ノンオイル)…1/2缶
・牛乳…大さじ1
・塩こしょう…少々
作り方
❶卵・牛乳・塩こしょうを混ぜる。
❷ツナを加えてざっくり混ぜ、フライパンで両面を焼く。
❸ケチャップを添えても◎
冷めても固くなりにくく、作り置きもOK!
③ 小松菜とちりめんじゃこのごま和え
ポイント: 非ヘム鉄+カルシウム+ビタミンCの三拍子!
材料(2〜3人分)
・小松菜…1束
・ちりめんじゃこ…大さじ2
・白ごま…大さじ1
・醤油…小さじ1
作り方
❶小松菜はさっと茹でて水気を切る。
❷全ての材料を和えるだけ!
作り置き可能。ごはんにのせても美味しいです。
🍽 家族みんなで食べられる貧血予防メニュー(1日分)
🥣【朝食】
✴︎ 鮭とほうれん草のスクランブルエッグプレート
✴︎ トマトとオレンジのサラダ
✴︎ ヨーグルト+はちみつ+ドライプルーン
✴︎ 全粒粉パン or 雑穀米のおにぎり
〜ポイント〜
鮭:ビタミンB12・鉄
ほうれん草:非ヘム鉄+葉酸
トマト&オレンジ:ビタミンCで鉄の吸収UP
ドライプルーン:鉄分が豊富で朝にぴったり
🍛【昼食】
✴︎ 牛肉とピーマンのオイスター炒め
✴︎ 小松菜としらすのごま和え
✴︎ わかめと豆腐の味噌汁
✴︎ 雑穀ごはん
〜ポイント〜
牛肉:吸収率の高いヘム鉄
ピーマン・小松菜:ビタミンC&鉄分
味噌汁:わかめでミネラル補給、豆腐でたんぱく質
雑穀米:鉄・マグネシウム・食物繊維が多い
🍴【夕食】
✴︎ 鶏レバー入りハンバーグ(または豆腐入りつくね)
✴︎ ブロッコリーとツナのサラダ(マヨ+レモン)
✴︎ ひじきと大豆の煮物
✴︎ かぼちゃの味噌汁
✴︎ 白米(または黒米・赤米を混ぜると栄養価UP)
〜ポイント〜
レバー:鉄分の宝庫(カレー味にしたりハンバーグに混ぜると子どもも食べやすい)
ツナ・ブロッコリー:ビタミン・たんぱく質・葉酸
ひじき:鉄分・カルシウム・食物繊維
かぼちゃ:ビタミンE、βカロテンで抗酸化サポート
🍮【間食・デザートにおすすめ】
・ドライフルーツ(プルーン、レーズン)
・黒ごまきな粉豆乳
・アーモンドミルクプリン
・いちごヨーグルト(鉄分入りヨーグルトがベター)
📝 ワンポイントアドバイス
✅ 鉄分の吸収を高める工夫
・ビタミンCを同時に摂る
・動物性たんぱく質と一緒に摂る(吸収率が上がる)
・コーヒーや緑茶は食後1時間以上あけて飲む
✅ 子どもがレバーを嫌がる場合
・レバーをみじん切りにしてハンバーグやミートソースに混ぜ込む
・鶏レバーをカレー風味や甘辛煮にすると食べやすい
◆ まとめ
貧血は「なんとなくだるい」「疲れやすい」といった漠然とした症状の背後に潜んでいることが多く、軽視されがちですが、放置すると日常生活に大きな影響を与えるばかりか、重篤な病気のサインであることもあります💡
「いつものことだから」と放置せず、気になる症状があれば当院にお気軽にご相談くださいませ。
早期発見・早期治療が何よりも大切です👌
その疲れやすさ・・・貧血かも?👀
2025.06.18