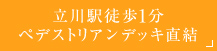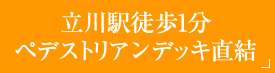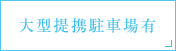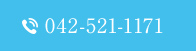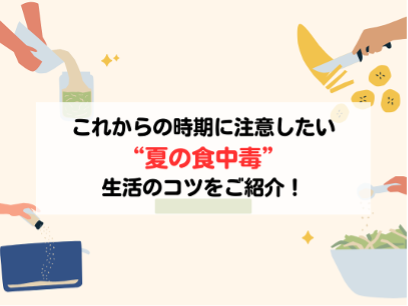
こんにちは🌻
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
日に日に日差しが強くなり、ムシムシとした湿気が肌にまとわりつくようになると、「いよいよ夏が来たなあ」と感じる方も多いのではないでしょうか❔この時期になると、特に気をつけなければならないのが「食中毒」です⚠️
気温と湿度が上がるこの季節は、食べ物の中で細菌やウイルスがどんどん繁殖しやすくなる
“食中毒シーズン”。
健康な方にとっても辛いものですが、特に胃腸が敏感になっている方や、慢性的な消化器疾患をお持ちの方にとっては、ほんの少しの油断が体調を大きく崩す原因にもなりかねません…
そこで今回は、「おいしく、楽しく、そして安全に」夏の食事を楽しんでいただけるよう、身近な食材でできる食中毒対策や、安心して食べられるお弁当のレシピ、ちょっとした保存のコツまで、わかりやすくお伝えいたします☝🏻読んでいただいた皆さまが、明日からすぐに実践できるヒントがたくさん詰まっていますので、ぜひ最後までお付き合いください💁♀️
■食中毒とは?その原因と症状🌡️
食中毒とは、細菌やウイルス、寄生虫、化学物質などの有害な物質が体内に入り込まれ、主に消化器に影響を与える病気の総称です。発症すると、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などのつらい症状が現れ、特に胃腸が弱っている方や免疫力が低下している方にとっては、重症化するリスクもあります。病原体の多くは、食べ物や飲み物を介して口から体に入り込みます。そして体内で増殖したり、毒素を出したりすることで、消化管の粘膜を傷つけ、さまざまな不快な症状を引き起こします。
以下は、夏に特に注意したい代表的な食中毒の原因です。
⚠️腸管出血性大腸菌(O157など)⚠️
いわゆる「O157」と呼ばれる菌は、牛などの家畜の腸内に自然に存在しています🥩この菌が混入した生肉や、加熱が不十分なハンバーグ、焼き肉、さらには汚染された野菜などを通じて体内に入ることで、激しい下痢や腹痛、血便などの症状を引き起こします。
特に注意すべきは、子どもや高齢者など免疫力が弱い方が感染すると、重症化しやすいという点です!
中には「溶血性尿毒症症候群(HUS)」という重篤な合併症を引き起こし、腎臓機能が低下したり、命に関わることもあります。
少し怖い話に思えるかもしれませんが、中心までしっかり加熱することでリスクはしっかり防げます。
特に、肉類は「見た目が焼けたからOK」ではなく、「中までしっかり火が通っているか」を意識しましょう!
⚠️カンピロバクター⚠️
日本で最も多く報告されている食中毒原因菌のひとつです。主に鶏肉や牛肉などの生肉、特に鶏の刺身や加熱不足の鶏料理から感染することが非常に多いです。
感染から1~7日ほどで症状が現れ、下痢・発熱・吐き気・腹痛などが出ます。多くの場合、症状は軽度~中等度ですが、まれに「ギラン・バレー症候群」という神経障害を引き起こすこともあるため、侮れません!鶏肉を扱う際は、調理前後にしっかりと手洗いを行い、器具を使い分けることが大切です🥢
⚠️ノロウイルス⚠️
冬のイメージが強いノロウイルスですが、実は夏でも感染することがあります。二枚貝(特にカキ)や汚染された水、または感染者の手指を介して広がることがあり、極めて感染力が強いのが特徴です。感染すると、突然の激しい嘔吐や水のような下痢、発熱が起こります。
小さなお子さんや高齢者にとっては、脱水症状に陥る危険性が高く、注意が必要です。
ウイルスはアルコールでは死滅しないため、石けんと流水での手洗いが有効です🖐🏻
■なぜ夏は危険なの?☀️
これらの病原体の多くは、20℃以上の温度で活動が活発になり、35~40℃付近で最も増殖スピードが高くなります。
つまり、人間や動物の体温と同じくらいの温度は、彼らにとって「最高の育成環境」なのです。
また、梅雨〜夏場にかけては湿度も高く、食品が傷みやすくなります。
調理から食べるまでのわずかな時間でも、菌はあっという間に増殖してしまうことがあります😱
特に、お弁当や作り置きのおかずなど、常温で保管する機会が多い食品は要注意です!
■食中毒予防の3原則👌🏻 ~家庭でもできる基本のき~
食中毒を防ぐうえで、とても大切なのが「予防の3原則」です。
この原則は、衛生管理の基本でもあり、一般のご家庭でも簡単に取り入れることができます。
是非参考にしてみてください✨
■3原則とは──
✅つけない(汚染防止)
細菌やウイルスを「食品に付けない」ようにすることが第一歩です!
目に見えない菌は、実は身の回りのどこにでも潜んでいます💣
たとえば、こんな場面で菌が食品に「ついて」しまうことがあります。
・生肉や魚を切ったまな板で、そのまま野菜も切ってしまった
・買い物帰りに手洗いをせずに、すぐ料理を始めた
・鶏肉を触ったあとに手を洗わずに冷蔵庫の取っ手を触った
こういった「うっかり」が、食中毒のきっかけになってしまうことも🌀
この“つけない”を守るためには、以下のことがとても効果的です。
・調理の前後やトイレの後、しっかりと手洗い(石けんと流水で20秒以上)
・生肉・生魚と生野菜などは、まな板・包丁を使い分ける、もしくは調理後すぐ洗って消毒する
・調理台や冷蔵庫の取っ手、キッチンクロスなども定期的に清潔に保つ
✅増やさない(温度管理)
菌は、食品の中で「増殖」することによって、食中毒のリスクを高めます。
特に気温が20℃を超えたあたりから、菌の増殖スピードは一気に加速⚡
中には、1時間で100万個にまで増えるものもあります(特に35~37℃では爆発的!)。
これを防ぐためには、「食品を適切な温度で管理する」ことが何より大切です。
・冷蔵すべきものは買ったらすぐ冷蔵庫に(4℃以下が目安)
・調理後のおかずはできるだけ早く冷ます。熱いまま保存容器に入れてふたをすると、雑菌が繁殖しやすくなります
・お弁当などは、保冷剤・保冷バッグを使い、常温で放置しない
また、夏場の買い物では、冷たい食材(肉・魚・乳製品など)は最後にかごに入れ、持ち帰ったらすぐ冷蔵庫へ!
このひと手間が、菌の増殖をぐっと抑えてくれます👌🏻
✅やっつける(加熱殺菌)
最後のポイントは、「食品に付いてしまった菌を死滅させる」こと。
加熱は、ほとんどの細菌に対して非常に効果的な“最終兵器”です🔥
食材を加熱する際には、「表面が焼けたからOK」ではなく、中までしっかり火が通ったかどうかを確認することが大切です。
加熱の目安は以下のとおりです。
・食品の中心温度が75℃で1分以上
・特に鶏肉、ひき肉料理(ハンバーグなど)、卵料理は丁寧に火を通す
・作り置きのおかずも、食べる前に全体がグツグツ沸騰するまで再加熱
また、電子レンジで加熱する際も、「外は熱いのに中は冷たい」ということが起こりやすいので、ラップをして全体にムラなく温める工夫も大切です!
■この3つを守れば、食中毒は防げる🎯
「つけない・増やさない・やっつける」──
この3原則は、一見シンプルですが、どれもとても実践的です。
そして何より、家庭でもすぐに取り入れられるものばかり*
ちょっとした油断や手抜きが、食中毒の原因になることがありますが、逆に言えば、少しの意識でリスクを大幅に減らすことができるのです。
家族の健康を守るためにも、自分自身の体調を守るためにも、毎日の食事作りにこの3原則をぜひ取り入れてみてくださいね😊
🍱お弁当作りでの食中毒予防ポイントをご紹介!
お弁当は、細菌が繁殖しやすい環境となるため、特に注意が必要です!
以下のポイントを心がけましょう。
❶手指の衛生管理
・調理前、トイレの後、動物に触れた後など、手を洗いましょう。
・手に傷がある場合、黄色ブドウ球菌が食品につき、食中毒を引き起こす可能性があります。
❷食材の取り扱い
・肉や魚を切った包丁、まな板はしっかり洗浄、消毒してから使いましょう。
・生の肉や魚などを調理したまな板などの器具から、野菜などへ菌が付着しないように注意しましょう。
❸加熱と冷却
・調理の際、中心部までしっかりと火を通しましょう。目安は中心部の温度が75℃で1分以上加熱することです。
・調理後の食品を温め直す時も全体が沸騰するまでしっかり加熱しましょう。
❹食材の選び方
・生の発芽野菜(アルファルファ、ヤエナリ、クローバー、ハツカダイコンなど)は、特に注意が必要です。
・生の果物や野菜は食べる前に入念に洗いましょう。
~食中毒予防に役立つお弁当レシピ3選!~
食中毒予防を考慮したお弁当レシピをご紹介いたします!
❶鶏むね肉のグリルと野菜のサラダ🥗
・鶏むね肉を中心部までしっかりと加熱し、グリルで焼きます。
・ミニトマトやレタスなどの生野菜は、食べる前にしっかり洗い、水気を拭き取ってから使用します。
❷野菜と豆の煮物🥕
・人参、大豆、じゃがいもなどを煮込み、中心部までしっかりと加熱します。
・煮物は冷ましてからお弁当に詰めると、細菌の増殖を防げます
・さらに、汁気をしっかり切って詰めるのもポイント。水分が多いと雑菌が繁殖しやすくなります。
・おすすめの具材は、ごぼう、人参、大豆、しいたけ、こんにゃくなど。煮物は冷めても味が落ちにくく、お弁当にぴったりです。
❸玄米おにぎり(抗菌おにぎり)
・おにぎりを握る際には、必ずラップやビニール手袋を使用しましょう。素手で握ると、手の常在菌が付着して繁殖する可能性があります。
・具材には「梅干し」「塩昆布」「わさび菜」「しょうが」など、抗菌作用が期待できる食材を選ぶと◎。
・また、焼きおにぎりにして表面をしっかり加熱してから冷ますのも安全性が高まります。
その他のおすすめレシピ🥄
|
おかず名 |
食材 |
ポイント |
|
鶏肉の柚子胡椒焼き |
鶏もも肉、柚子胡椒、酒 |
柚子胡椒の抗菌作用に期待! |
|
卵焼き(甘くないだし巻き) |
卵、だし、塩 |
しっかり加熱して芯まで火を通す。 |
|
ブロッコリーのおかか和え |
茹でブロッコリー、 |
茹でて水分を飛ばし、鰹節で抗酸化作用もUP。 |
|
梅きゅうり漬け |
きゅうり、梅干し、酢 |
酸味で菌の繁殖を抑える。 |
■お弁当の保存と持ち運びのコツ🧊
いくら加熱や衛生面に注意しても、保存状態が悪ければ食中毒のリスクは高まります!
特に夏場のお弁当は、持ち運び時の温度管理がとても重要です。
保存の工夫
・お弁当は必ず冷ましてからフタを閉めましょう。熱いままフタをすると水蒸気がこもり、雑菌が繁殖しやすくなります。
・保冷剤や保冷バッグを活用して、持ち運び中も低温を保ちましょう。
・職場や学校に冷蔵庫がある場合は、必ずそこに保管しましょう。
・食べる前には電子レンジなどで再加熱できると、さらに安全です。
~消化器疾患がある方への特別アドバイス~
消化器内科で診ている患者さんの多くは、胃腸の抵抗力が弱くなっていることがあります。
そのため、食中毒は一般の人より重症化しやすいのです。
胃腸の症状をお持ちの方は、以下の点に特に注意してください⚠️
・免疫力が低下している方(抗がん剤治療中、慢性疾患のある方など)は、非加熱食品をなるべく避けましょう。サラダや刺身などは要注意です。
・胃を部分的に切除している方などは、胃酸による殺菌効果が弱くなっているため、より慎重な食事管理が求められます。
・整腸剤や抗生物質を服用中の方は、腸内環境が乱れているため、少量の菌でも腹痛や下痢を起こしやすくなります。
■まとめ 〜夏を元気に乗り切るために📝〜
食中毒は、ちょっとした気の緩みで発生します!
しかし、ちょっとした工夫でも大きく防ぐことができます。
🔸 手洗いの徹底
🔸 しっかり加熱、しっかり冷却
🔸 ラップや手袋の使用で「つけない」工夫
🔸 抗菌作用のある食材の活用
🔸 持ち運びと保存に「保冷」対策を忘れずに
これからの暑い季節を、健康に、そして笑顔で過ごせるよう、ぜひこの食中毒対策を日常生活に取り入れてみてくださいね👌🏻
暑い日が続いており、胃腸の不調の患者さまも増えております。内視鏡検査については、「痛くない・辛くない・恥ずかしくない」胃カメラ検査・大腸カメラ検査に取り組んでおりますので、胃腸に関する気になる症状や胃腸炎などの症状などございましたら、お気軽にご相談くださいませ*