肛門科について
 当院の肛門科では、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、肛門周囲膿瘍、あな痔(痔瘻(痔ろう))など、肛門に関する様々な疾患の診療を行っております。
当院の肛門科では、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、肛門周囲膿瘍、あな痔(痔瘻(痔ろう))など、肛門に関する様々な疾患の診療を行っております。
「肛門の診察に抵抗がある」「恥ずかしい」というお気持ちにもしっかり配慮し、安心して受診して頂けるよう、プライバシーに配慮した診療体制を整えています。
肛門の痛み・出血・かゆみ・腫れ・便通の異常など、少しでも気になる症状がありましたら、悪化する前に早めのご相談をお勧めします。
以下のような症状がある方は
ご相談ください
- 肛門に痛みやかゆみがある
- 排便時あるいは排便後にヒリヒリとした痛みを感じる
- 便に血が混じる、あるいは肛門から出血する
- 肛門の周りが腫れている
- 肛門からいぼのようなものが出ている
- 肛門にしこりやできものがある
- 排便時にスムーズに便が出ない
- 便が細くなったと感じる
肛門に関連する主な疾患
いぼ痔(痔核)
いぼ痔は、医学的には「痔核」と呼ばれ、肛門付近にいぼ状の腫れができる疾患です。出血や痛みを伴うことが多く、排便時の強いいきみや便秘、排便の我慢、長時間の座り姿勢といった生活習慣が原因とされています。痔核は、発生する場所によって「内痔核」と「外痔核」に分類されます。
内痔核
内痔核は、肛門の粘膜と皮膚の境界である「歯状線」の内側にできる痔です。初期段階では、排便時にいぼが一時的に出てきますが、自然に戻ることがほとんどです。進行すると、いぼが常に外に出たままになり、指で押しても引っ込みにくくなります。出血は見られますが、基本的に痛みは伴いません。
外痔核
外痔核は、歯状線より外側、つまり肛門の皮膚側に発生する痔です。内痔核と異なり、強い痛みを伴うことがあり、出血を伴うケースもあります。
切れ痔(裂肛)
切れ痔は医学的には「裂肛」と呼ばれ、肛門の皮膚が裂けてしまうことで、ヒリヒリとした痛みや出血が起こる病気です。主な原因には、硬い便や慢性的な下痢などがあります。排便時に鋭い痛みを感じたり、少量の出血がトイレットペーパーに付着して気づくこともあります。
肛門周囲膿瘍
歯状線の内側にあるくぼみに細菌が侵入することで、肛門周囲に膿が溜まる疾患です。主な症状には、肛門の腫れや痛みなどがあり、原因としては便秘や下痢、免疫力の低下、ストレス、大腸疾患などが関係しています。進行すると、肛門と皮膚を繋ぐトンネル(瘻管)が形成される場合があります。
あな痔(痔瘻)
痔瘻は、肛門周囲膿瘍が悪化し、肛門内部と皮膚表面が細い管(瘻管)で繋がってしまう病気です。膿が排出されたり、痛み・腫れ・かゆみを引き起こすほか、長期間放置すると瘻管が枝分かれして複雑化することがあります。重度になると、発熱や全身の倦怠感が現れることもあります。
肛門科における診療の流れ
1問診票の記入
 まずは症状やご体調についてWEB問診もしくは問診票への入力をお願いいたします。分かる範囲でご記入をお願いいたします。
まずは症状やご体調についてWEB問診もしくは問診票への入力をお願いいたします。分かる範囲でご記入をお願いいたします。
2医師による問診
 恥ずかしさに配慮するため問診内容をもとに診療が進みます。
恥ずかしさに配慮するため問診内容をもとに診療が進みます。
肛門に関するお悩みはデリケートな内容を含むことが多いため、プライバシーに十分配慮した上で、必要な情報について問診を追加で取ることがあります。
3診察・検査
 診察では、視診・触診などの基本的な検査を行います。タオルで患部以外を覆うなど、できる限り恥ずかしさを感じさせない工夫をしながら進めてまいりますので、ご安心ください。
診察では、視診・触診などの基本的な検査を行います。タオルで患部以外を覆うなど、できる限り恥ずかしさを感じさせない工夫をしながら進めてまいりますので、ご安心ください。
また、痛みにも配慮するためお声がけのほか、潤滑ゼリーをしっかり用いて、痛みが強い場合には状況に応じて診察、検査を施行します。できる限り痛み苦痛が少ない状態を目指します。女性の患者様には原則女性スタッフの同席があります。
4診断と治療のご提案
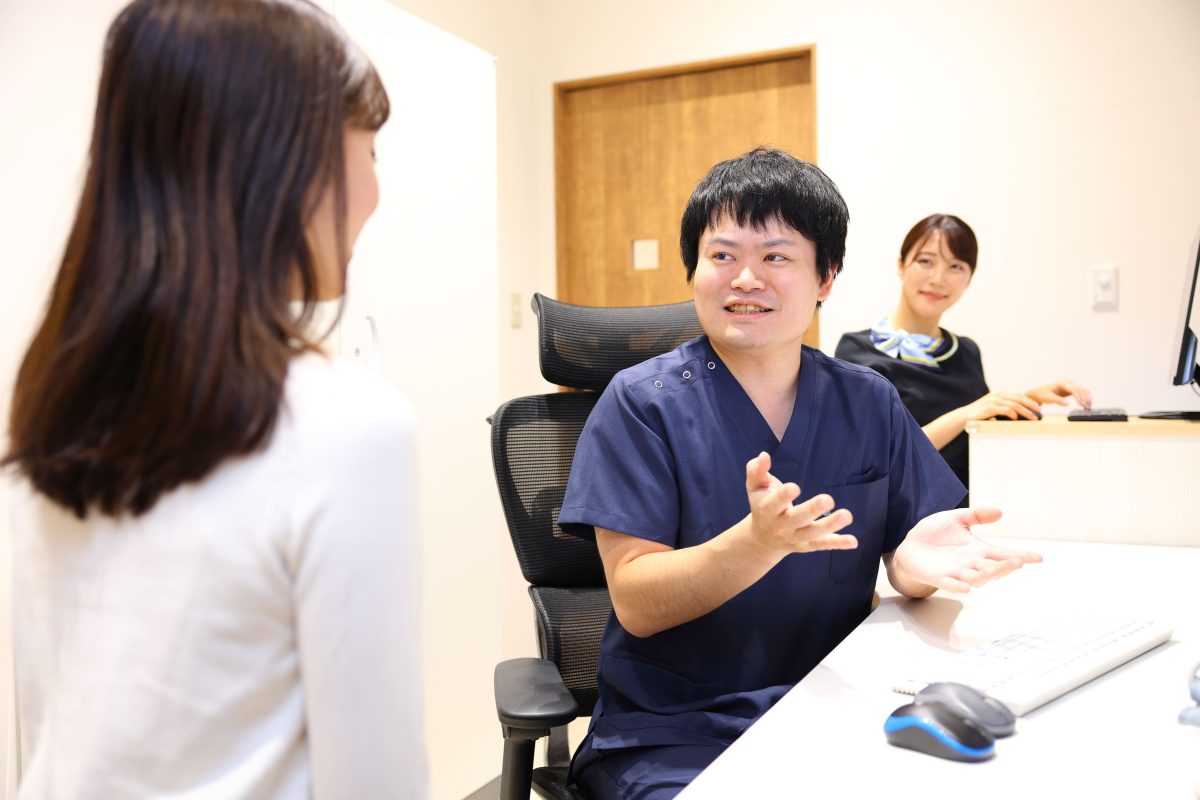 これまでの診察結果を総合的に判断し、診断を行います。その上で、治療の選択肢をご説明し、ご理解・ご納得頂いた上で治療を開始いたします。
これまでの診察結果を総合的に判断し、診断を行います。その上で、治療の選択肢をご説明し、ご理解・ご納得頂いた上で治療を開始いたします。
肛門疾患の悪化や再発を
防ぐために心がけたいこと
排便習慣の見直し
排便に関する指導を受ける機会はあまり多くありませんが、肛門疾患と排便習慣は密接に関わっています。当院では現在の排便状況をお伺いし、必要に応じて医師が生活に即したアドバイスを行います。
排便の際には、以下の点を意識しましょう。
- 便秘や便が硬い場合には、便が柔らかくなるよう水分摂取や緩下剤を飲む。
- 毎日できるだけ決まった時間にトイレへ行く習慣をつける(便意がなくても座ってみる)
- 便意を我慢しない
- 無理に強くいきまない
- 3分以上かかる場合は無理をせずいったん切り上げる
- 背筋を伸ばすよりも、少し前かがみになることで直腸が伸び、排便しやすくなります
また、しゃがむ姿勢が肛門に負担をかけやすいため、和式トイレの使用はなるべく避けるのが望ましいでしょう。
温水洗浄便座(ウォシュレット)の正しい使用方法
肛門に刺激を与えないよう、温水洗浄便座を使用する際は以下の点にご注意ください。
- 洗浄は「普通」から「弱め」の水圧で、時間は5秒以内に留める
- 肛門の中まで洗浄しない(外側の便を軽く洗い流す目的で使用する)
- 洗浄機能による刺激で排便を促すような使い方は避ける(便意が起こりにくくなります)
食習慣の改善
 便秘や下痢を予防するには、日々の食習慣が重要です。暴飲暴食やアルコールの過剰摂取、香辛料など刺激の強い食べ物は控えましょう。
便秘や下痢を予防するには、日々の食習慣が重要です。暴飲暴食やアルコールの過剰摂取、香辛料など刺激の強い食べ物は控えましょう。
便秘傾向のある方は、水分をしっかり摂りつつ、食物繊維の摂取も意識してください。
食物繊維には以下の2種類があり、バランス良く取り入れることが大切です。
- 水溶性食物繊維(腸内環境を整え、便を柔らかくします)
- 不溶性食物繊維(腸を刺激し、排便を促します)
水溶性食物繊維を多く含む食品
- 海藻類:昆布、わかめ、もずくなど
- 果物:りんご、キウイ、みかんなどの柑橘類など
- いも類:さつまいもなど
- 野菜:オクラ、なす、ごぼうなど
不溶性食物繊維を多く含む食品
- 野菜:ゴボウ、ブロッコリー、かんぴょう、ホウレンソウなど
- 豆類:花豆、えんどう豆、あずき、枝豆など
- 果物:カキ、リンゴ、キウイ、アボカドなど
- きのこ類:エリンギ、干しシイタケなど
- 穀物:穀類(玄米など)
運動習慣の改善
 適度な運動は、腸の動きを活性化させ、自律神経のバランスを整えることで排便をスムーズにします。
適度な運動は、腸の動きを活性化させ、自律神経のバランスを整えることで排便をスムーズにします。
一方で、長時間座りっぱなしの姿勢は肛門への圧力や血流の悪化を招き、痔の悪化に繋がる可能性があります。
デスクワークの方は、こまめに立ち上がって体を動かしたり、軽くストレッチを取り入れる習慣をつけましょう。
また、肛門の負担を和らげるクッション(ドーナツ型など)を活用するのも効果的です。













