不眠症について
 不眠症は、「寝つけない」「夜中に目が覚める」「熟睡できない」といった睡眠に関する問題が継続し、その結果として日中の集中力低下や疲労感などの不調を引き起こす状態です。
不眠症は、「寝つけない」「夜中に目が覚める」「熟睡できない」といった睡眠に関する問題が継続し、その結果として日中の集中力低下や疲労感などの不調を引き起こす状態です。
日本では、成人の約5人に1人が何らかの睡眠の悩みを抱えているとされており、不眠症は特別な病気ではなく、誰にでも起こりうる身近な症状です。
眠る時間や睡眠の質には個人差があり、短時間でも十分休める人がいる一方、長時間眠っても満足感が得られない方もいます。
「自分は病気ではない」「不眠症とは違う」と思い込んでしまう方も多いのですが、日常生活に支障が出るようであれば、医療機関に相談することが大切です。
本来、良質な睡眠とは“無理に寝ようとする”ものではなく、心身がリラックスした状態で自然に訪れるものです。
不眠症の4つのタイプ
不眠症には以下のようなタイプがあり、それぞれに合った対処が必要です。当院では、症状の種類や背景に応じたきめ細やかな治療を行っています。
- 入眠障害:寝つきに時間がかかり、なかなか眠れない
- 途中覚醒:夜中に何度も目が覚めてしまう
- 早朝覚醒:朝早くに目が覚め、その後眠れない
- 熟眠障害:睡眠時間は確保できているのに熟睡感が得られない
不眠症を引き起こす原因
環境・心理的ストレス
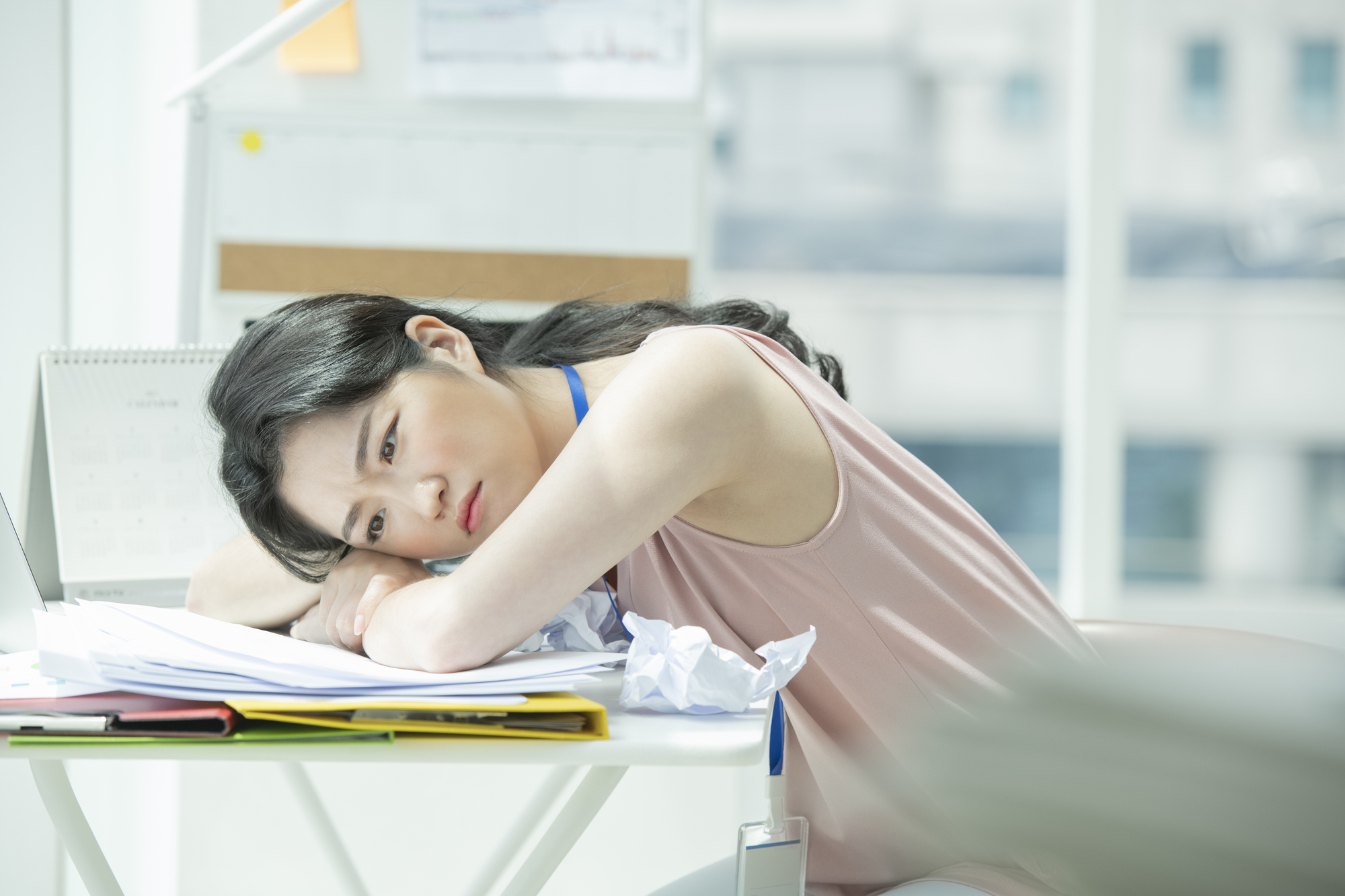 家庭や職場のストレスが続くことで、心が休まらず睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
家庭や職場のストレスが続くことで、心が休まらず睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
生活習慣病などの疾患
高血圧や糖尿病などの疾患がうまくコントロールされていないと、体調不良から不眠に繋がることがあります。また、十分な睡眠が取れないことにより、これらの病気が悪化するという相互関係も見られます。
アルコール・カフェイン
「寝酒」としてアルコールを利用する方も少なくありませんが、一時的に寝つきは良くなるものの、浅い睡眠となり、途中で目覚めやすくなります。次第に飲酒量が増えて依存に陥るケースもあり、悪循環に注意が必要です。
実は、適切に使えば睡眠薬の方が副作用は少なく、安全に眠れる場合もあります。
また、コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインの摂りすぎも、寝つきを妨げる原因となります。
薬物療法
睡眠薬の役割と種類
 不眠症には、寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に目が覚める「中途覚醒」、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」、眠った感じが得られない「熟眠障害」などのタイプがあります。それぞれの症状に応じて、適切な種類の睡眠薬を選ぶことが大切です。
不眠症には、寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に目が覚める「中途覚醒」、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」、眠った感じが得られない「熟眠障害」などのタイプがあります。それぞれの症状に応じて、適切な種類の睡眠薬を選ぶことが大切です。
「睡眠薬は依存性がある」「認知症のリスクがある」といった不安を感じる方も多いかもしれませんが、現在使用されている薬剤の多くは、ベンゾジアゼピン系または非ベンゾジアゼピン系と呼ばれるもので、脳内の神経活動を調整し、眠気を促す作用があります。
効果が確実な一方で、長期間使用すると依存性や効果の減弱が見られることもあるため、医師の管理のもとで適切に使用することが重要です。
また、最近では、睡眠や覚醒に関わる脳内物質である「メラトニン」や「オレキシン」に作用する新しいタイプの睡眠薬も登場しています。
これらは特に「熟睡感の向上」に有効とされますが、個人の代謝の違いにより効果には差が出る場合があります。
快適な睡眠には「心の安定」も重要です
 子どもの頃、特に眠ろうと意識しなくても自然と眠れていた経験はありませんか。
子どもの頃、特に眠ろうと意識しなくても自然と眠れていた経験はありませんか。
「お薬を飲んでも眠れない」「眠っても休んだ気がしない」といった悩みを抱える方の中には、心の不調が背景にあるケースも少なくありません。怖い夢を繰り返し見る、数種類の睡眠薬を試しても改善しないといった場合、心の状態を整えることが快眠への近道となります。
人間の感情や思考は、脳内で働く神経伝達物質によって支えられています。そのバランスが崩れると、眠りにも影響が出てしまいます。精神的なストレスを和らげ、脳の状態を健やかに保つことが、質の良い眠りへと繋がっていくのです。
1日の終わりに、不安や嫌な出来事を思い返すよりも、「今日の良かったこと」「明日の楽しみ」など、前向きなイメージを思い浮かべて布団に入ってみてください。そうした気持ちの切り替えが、最良の“天然の睡眠薬”になることもあります。













