内痔核について
 内痔核は、肛門の内側にある血管がうっ血し、膨らんで痔核(こぶ)のように膨らんだ状態です。痔は大きく「内痔核」と「外痔核」の2つに分類されますが、内痔核は肛門管の内側にある「静脈叢(じょうみゃくそう)」と呼ばれる血管の集まりが拡張してできるのが特徴です。
内痔核は、肛門の内側にある血管がうっ血し、膨らんで痔核(こぶ)のように膨らんだ状態です。痔は大きく「内痔核」と「外痔核」の2つに分類されますが、内痔核は肛門管の内側にある「静脈叢(じょうみゃくそう)」と呼ばれる血管の集まりが拡張してできるのが特徴です。
肛門内部には痛みを感じる神経が少ないため、初期の内痔核は外見からは分かりにくく、自覚症状も乏しい場合がほとんどです。
しかし、痔核が大きくなると排便時に出血したり、進行すると肛門の外へ脱出する「脱肛」を起こすことがあります。
脱出した痔核が自然に戻らない場合は、指で押し戻す必要が生じることもあり、炎症や腫れを伴うと痛みを感じるようになります。
内痔核の原因には、慢性的な便秘や下痢、排便時の過度ないきみ、妊娠中の骨盤内圧の上昇、長時間座りっぱなしの生活、加齢による組織の弾力低下などが挙げられます。
これらは肛門周囲の血流を悪化させ、静脈叢に負担をかけることで痔核の形成を引き起こします。
治療法は、症状の程度や患者様の全身状態によって異なります。
軽度の場合は、軟膏と坐薬といったお薬による局所薬剤療法の他、食生活の改善や水分・食物繊維の摂取、排便習慣の見直しなど、生活習慣の調整で改善が期待できます。
まずは薬での治療が基本ですが、進行した場合は、手術や硬化療法など、より専門的な治療が必要になることもあります。
出血や脱肛に気付いたら早めに受診して検査を受け、適切な治療につなげることが重要です。
なお、内痔核は、進行度によって4段階に分けられています。
内痔核の主な症状
内痔核に見られる代表的な症状は以下の通りです。
出血
排便時に鮮やかな赤色の出血が見られることがあり、便の表面やトイレットペーパーに血が付着することがあります。
不快感・痛み
痛みは最初は目立ちませんが、痔核が大きくなることで、肛門内に圧迫感や異物感を覚えることがあります。脱肛や炎症を伴うと、痛みが強くなることもあります。
腫れ
肛門内の血管が腫れることで、圧迫されるような感覚が現れることがあります。
脱出(脱肛)
重症になると、痔核が排便時に肛門の外に出てしまい、自然に戻らなくなるケースもあります。このような場合には、手で押し戻す必要があります。
かゆみ
肛門周囲の皮膚が刺激されることにより、かゆみを伴うこともあります。
これらの症状は、内痔核に限らず、他の肛門疾患や消化器疾患とも共通する場合があるため、正確な診断が必要です。異常を感じた場合は、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。
内痔核と大腸疾患の関係について
内痔核は、直接的に大腸の病気によって発生するわけではありませんが、大腸の機能や消化器の状態が影響を及ぼし、痔核の発症や悪化に関与することがあります。以下は、内痔核との関連が指摘されている大腸疾患や消化器の状態です。
内痔核に影響を与える大腸疾患や消化器の異常
便秘
 長期的な便秘は排便時のいきみを強め、肛門内の血流を悪化させることで内痔核の形成や悪化の一因となります。
長期的な便秘は排便時のいきみを強め、肛門内の血流を悪化させることで内痔核の形成や悪化の一因となります。
便秘は大腸の運動機能の低下によって引き起こされることがあります。
下痢
繰り返す下痢も肛門への刺激が強く、結果的に痔核を発症・悪化させる原因になることがあります。
大腸がん
極めて稀ではありますが、大腸がんが便秘や排便困難を招き、結果として肛門への圧力が増すことで、内痔核の形成に関与する可能性があります。
内痔核の治療方法
内痔核の治療は、症状の程度や患者様の体調・生活スタイルに応じて選択されます。まずは生活習慣の改善から取り組み、効果が不十分な場合には、医療的な治療が検討されます。
生活習慣の改善
食物繊維の摂取
 野菜、果物、全粒穀物など、繊維質の多い食品を積極的に取り入れることで、便通の改善を図ります。
野菜、果物、全粒穀物など、繊維質の多い食品を積極的に取り入れることで、便通の改善を図ります。
水分補給
 水分をしっかり摂ることで便を柔らかく保ち、排便時の負担を軽減します。
水分をしっかり摂ることで便を柔らかく保ち、排便時の負担を軽減します。
適度な運動の習慣化
 ウォーキングなどの軽い運動は腸の動きを促進し、便秘の予防に繋がります。
ウォーキングなどの軽い運動は腸の動きを促進し、便秘の予防に繋がります。
排便習慣の見直し
長時間のトイレ滞在や過度ないきみは避け、規則正しい排便リズムを作ることが重要です。
医療的なアプローチ
薬物療法
まず最初は、軟膏と坐薬といったお薬による局所薬剤療法を開始します。しっかり使用することで十分な効果が見込めます。継続することが重要です。同時に、硬い便や便秘、下痢がある場合には、便通管理のため、下剤、緩下剤、整腸剤を処方し内服にて便通管理も施行します。
結紮療法(輪ゴム結さつ術)
痔核の根元に特殊なゴムバンドをかけて血流を遮断する方法で、数日で自然に痔核が脱落します。当院では対応しておりません。
硬化療法(注射療法)
ALTA療法(アルタ療法)が近年主体となっています。痔核に硬化剤を注入して血管に炎症を惹起し痔核を硬化し縮小させる治療です。
ジオン注射(ALTA療法)の適応となるものは、原則内痔核、内側のいぼ痔です。外痔核、外側のいぼ痔にはジオン注射は適応外となります。医師が適応判断するため、必ずご希望に添えるわけではございません。事前にご相談ください。
手術(手術療法が必要な場合は原則紹介となります。薬物療法を主に行っております。)
他の治療で効果が不十分な場合には、痔核を切除する手術や、血流をコントロールする外科的処置が選択されます。
結紮切除術
内痔核が大きく、軟膏や座薬による保存的治療での改善が困難な場合に行われる手術です。痔核を結紮(縛って)切除する方法が多く用いられます。
手術施行時に、ジオン注射(ALTA療法)を併用して行うことがあり、ALTA併用療法ともいいます。入院が必要な手術ですが、現在では出血や切除に伴う痛みを最小限に抑える手術が可能になっており、徐々に日帰り手術を施行している施設も増えてきています。
症状、所見と患者さまのご希望に応じて、適切な医療機関へご紹介させていただきます。術後は数日間、痛みが起こる可能性がありますが、座薬や内服薬による緩和が可能です。当院で手術療法は施行しておりません。
PPH法
特殊な器具で痔核への血行を遮断した上で痔核を持ち上げ、自動吻合器という機械で直腸粘膜を一括切除する手術器械を用いて、縫い合わせる手術です。
術後の痛みも抑えることができ、回復も早くなりますが、万一、直腸粘膜の吻合部がくっつかなかった場合は縫合不全という合併症となります。
また手術後に肛門周囲の浮腫が強く表れたり、感染を起こすことがあり、リスクも有る手術といえます(手術費用も高額になります)。なお、PPH法は1993年にイタリアで開発された手術法であり、日本では2008年に保険適用となっています。当院でPPH法は施行しておりません。
内痔核の治療は、症状の程度や患者様の生活環境によって適した方法が異なります。自己判断で治療を遅らせることは避け、症状がある場合は早めに医療機関を受診し、正確な診断と治療方針について医師の指導を受けることが大切です。
ALTA療法について
ALTA療法(アルタ療法)は、内痔核に対する非手術的な治療法の1つで、特に日本国内で広く用いられている方法です。
「ALTA」とは、有効成分であるアルミニウム(Aluminum)・リン酸(Phosphate)・タンニン(Tannin)・酢酸(Acetate)の頭文字を取った名称で、この薬剤を痔核内に注射することで、痔核を硬化・縮小させることを目的としています。
ALTA療法の流れ
1局所麻酔の実施
治療を行う内痔核に対して、まず局所麻酔を行います。
2ALTA薬剤の注射
ALTAを痔核の内部にある4層(粘膜下層、痔核内層、痔核中層、痔核の根部周囲)へ段階的に注入していきます。
3硬化・縮小反応
薬剤が組織内で作用し、痔核の血流が遮断されることで、徐々に組織が硬くなり縮小していきます。
ALTA療法のメリット
手術を行わない治療法
メスを使わないため、身体的な負担が少なく、日常生活への復帰も早いとされています。
局所的に高い効果
痔核に直接薬剤を注入することで、ピンポイントに効果を発揮しやすいです。80%以上の症例で硬化が見込まれます。
ALTA療法に関する注意点
適応の限界
ALTA療法は全ての内痔核に対応できるわけではありません。強い炎症がある場合や脱出が頻繁な痔核などには適さないことがあります。
手術と比較した再発率
手術と比較した場合、ALTA療法は若干再発率が高いという報告もあります。
副作用の可能性
治療後に注射部位の腫れや痛みが現れることがあり、稀にアレルギー反応が起こるケースも報告されています。また、術後発熱を来すことがあります。
ALTA療法は、切らずに治すことが可能な内痔核治療の選択肢として、多くの患者様にとって有益な方法ですが、全ての症例に適しているわけではありません。
治療を受ける際は、医師と十分に相談し、ご自身の症状や健康状態、治療のリスク・効果を総合的に検討したうえで、適切な方針を決定することが大切です。
外痔核について
外痔核は、肛門の外側に発生する腫れや突起で、痛みを伴うことが多い痔疾患の1つです。肛門周囲の静脈がうっ血して膨らむことで形成され、外見上確認できたり、触れて認識できたりする点が、内痔核との大きな違いです。
主な原因としては、便秘や長時間の座りっぱなし、妊娠・出産、遺伝的要因などがあり、肛門に強い圧がかかる状況が発症に関与するとされています。
血栓性外痔核について
血栓性外痔核は、外痔核の一種であり、肛門周囲の静脈内に血栓(血の塊)ができて発症する状態です。
突然の激しい痛みとともに、肛門周囲に赤紫色〜青みがかった硬いしこりが生じるのが特徴で、多くの場合、日常生活にも支障をきたすほどの強い不快感を伴います。
血栓性外痔核では次のような症状がよく起こります。
- 急激に現れる肛門周囲の鋭い痛み
- 押すと痛みを感じる硬い腫れ
- 赤みや腫脹を伴う場合がある
- 排便時に痛みや違和感を覚える
この状態は、過度ないきみ、長時間の座位、妊娠・出産、重いものを持つ動作などが引き金となって発症することが多いとされています。
血栓性外痔核の治療は、症状の程度に応じて保存的治療(軟膏や坐薬などの薬剤治療)と外科的治療が検討されます。軽度から中等度の血栓性外痔核に対しては、まず保存的治療(軟膏や坐薬などの薬剤治療)が行われます。
具体的には、ステロイドや局所麻酔成分を含んだ軟膏や坐薬、鎮痛薬の使用、冷却療法、温浴療法、食事療法などが挙げられます。発症早期であり痛みが強い場合には、血栓の外科的摘出が行われることもあります。
外痔核の治療方法
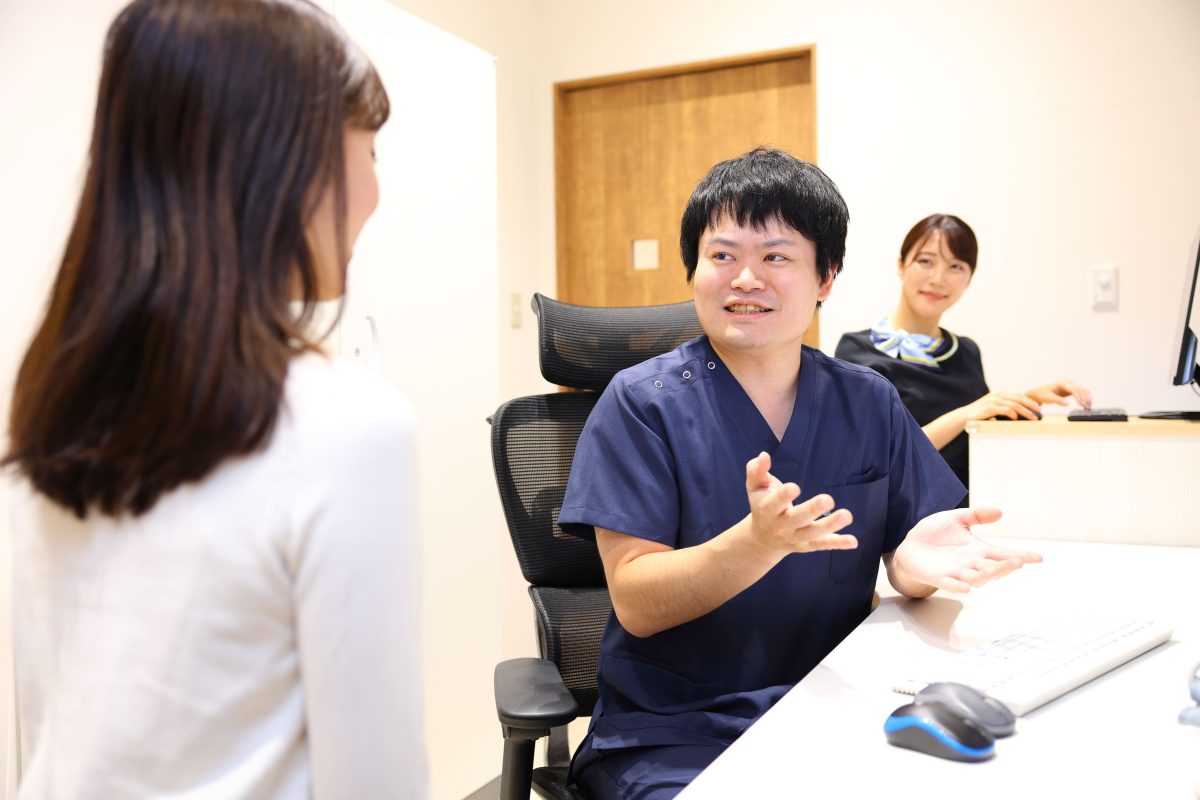 外痔核の治療は、症状の程度や生活背景に応じて段階的に行われます。
外痔核の治療は、症状の程度や生活背景に応じて段階的に行われます。
自宅での対処法(生活習慣の改善)
食物繊維の摂取
食物繊維の多い野菜、果物、全粒穀物を取り入れ、便秘の予防に努めます。
水分補給
便を柔らかく保つため、日常的に十分な水分を摂取します。
シッツバス
肛門周囲を温めることで血流を促進し、痛みや腫れを和らげます。
排便習慣の見直し
便通管理、便秘下痢がないよう食生活などを見直し、改善ない場合には受診する。
長時間のトイレ滞在や過度ないきみは避け、規則正しい排便リズムを作ることが重要です。
適正体重の維持
肥満は痔のリスクを高めるため、適正体重を保ちましょう。
運動習慣の確立
運動を習慣化することで、便秘予防と血行促進が期待できます。
長時間座ることを避ける
時折立ち上がり、歩くことを心がけましょう。
医療機関での処置・処方
薬物療法
まず最初は、軟膏と坐薬といったお薬による局所薬剤療法を開始します。しっかり使用することで十分な効果が見込めます。継続することが重要です。同時に、硬い便や便秘、下痢がある場合には、便通管理のため、下剤、緩下剤、整腸剤を処方し内服にて便通管理も施行します。
手術(手術療法が必要な場合は原則紹介となります。薬物療法を主に行っております。)
重度で他の治療で改善しない場合や繰り返す場合には、痔核を外科的に切除します。
外痔核や血栓性外痔核は、早期に適切な治療を受けることで改善が期待できます。強い痛みや出血が続く場合、また症状が慢性的に繰り返すようであれば、早めに医療機関を受診し、正確な診断と適切な治療方針を相談することが重要です。
手術
外痔核の切除
重度で他の治療で改善しない場合は、痔核を外科的に切除します。
生活習慣の改善
適正体重の維持
肥満は痔のリスクを高めるため、適正体重を保ちましょう。
運動習慣の確立
運動を習慣化することで、便秘予防と血行促進が期待できます。
長時間座ることを避ける
時折立ち上がり、歩くことを心がけましょう。
外痔核や血栓性外痔核は、早期に適切な治療を受けることで改善が期待できます。強い痛みや出血が続く場合、また症状が慢性的に繰り返すようであれば、早めに医療機関を受診し、正確な診断と適切な治療方針を相談することが重要です。













