- 花粉症について
- 花粉症を引き起こす原因
- 花粉症の種類
- 花粉症の主な症状
- 花粉症の検査・診断方法
- 花粉症の初期療法
- 花粉症の治療方法
- 花粉症の予防方法
- 花粉症治療時の注意点
- セルフケアとしての市販薬活用
- 花粉症でお悩みの方は当院までご相談ください
花粉症について
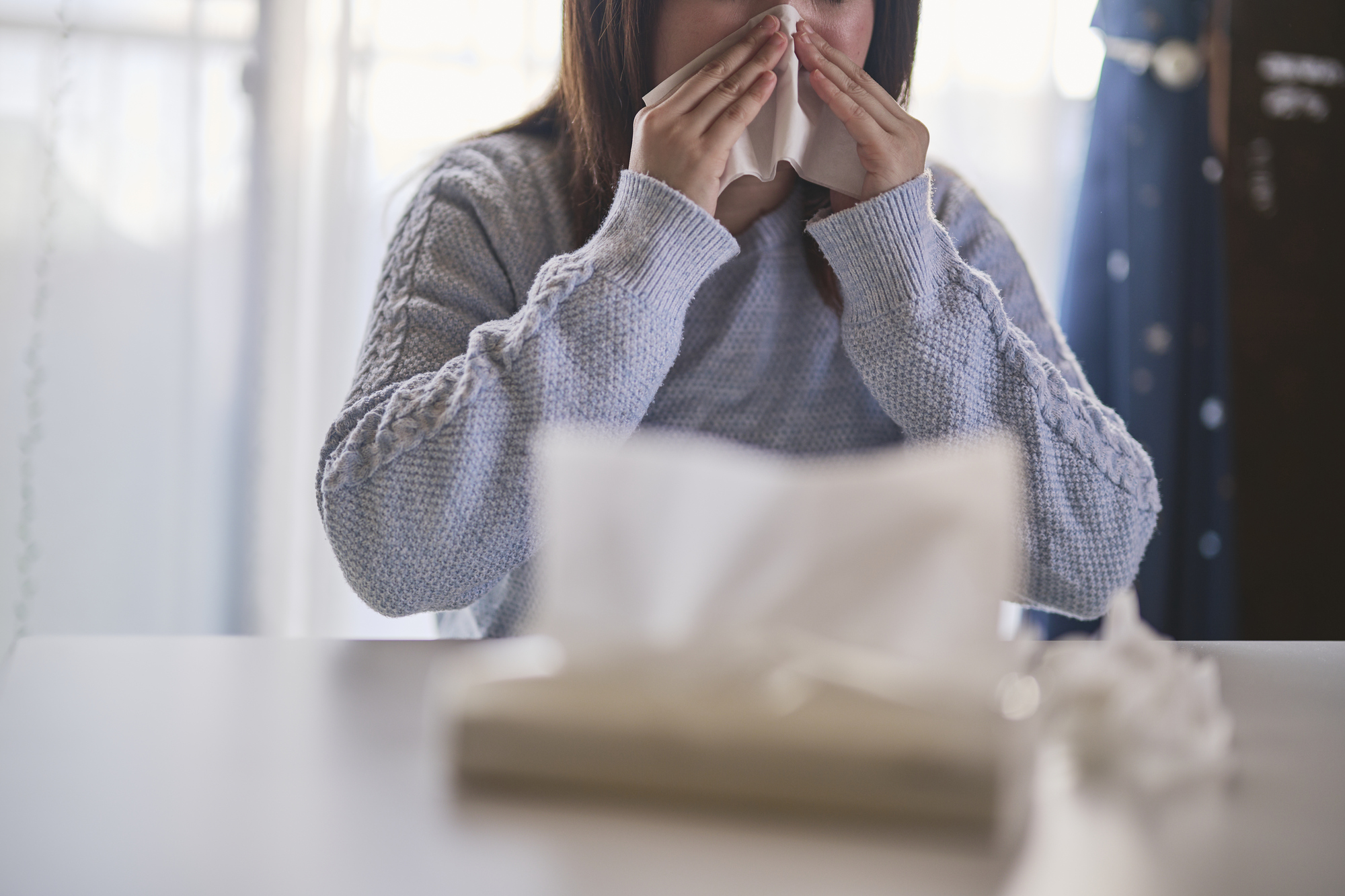 花粉症は「季節性アレルギー」とも呼ばれ、スギやヒノキなどの植物の花粉が体内に入ることでアレルギー反応を引き起こす病気です。
花粉症は「季節性アレルギー」とも呼ばれ、スギやヒノキなどの植物の花粉が体内に入ることでアレルギー反応を引き起こす病気です。
日本では、特にスギ花粉による花粉症の患者様が多く、約4割の人が発症しているとされています。
症状としては、鼻水や目のかゆみといったアレルギー反応が見られます。
花粉症を引き起こす原因
花粉症は、花粉が鼻やのど、目の粘膜に付着することで免疫反応が起こるアレルギー性疾患です。体内に侵入した花粉をリンパ球が異物として認識すると、「IgE抗体」と呼ばれる物質が作られます。この抗体が作られた後、再び花粉が体内に入ると、鼻や目の粘膜に存在する肥満細胞とIgE抗体が結合し、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質が放出されます。
これらの化学物質は神経や血管を刺激し、体外に花粉を排出しようとする働きによって、くしゃみ・鼻水・涙などの症状が引き起こされます。
「昨年までは平気だったのに、今年から急に花粉症になった」というケースは少なくありませんが、それは体内に蓄積されたIgE抗体の量が一定のレベルに達し、反応が発現したためと考えられています。
花粉症の種類
 花粉症の原因となる植物には、スギやヒノキをはじめ、イネ、ヨモギ、カモガヤ、ブタクサ、シラカンバなど様々な種類があります。これらは植物ごとに飛散時期や地域の分布が異なるため、花粉の飛ぶ時期を把握しておくことで、早めの対策が可能になります。
花粉症の原因となる植物には、スギやヒノキをはじめ、イネ、ヨモギ、カモガヤ、ブタクサ、シラカンバなど様々な種類があります。これらは植物ごとに飛散時期や地域の分布が異なるため、花粉の飛ぶ時期を把握しておくことで、早めの対策が可能になります。
なかでもスギ花粉症は患者数が多く、全国の森林の約18%、国土の約12%をスギが占めている日本では、花粉症全体の約7割がスギ花粉によるものと考えられています。関西地方では、スギに加えてヒノキの植林も多いため、ヒノキ花粉による症状にも注意が必要です。
一方、北海道ではスギやヒノキの植生は少なく、代わりにシラカンバが多く分布していることから、シラカンバによる花粉症が多く見られます。
花粉の種類とピーク時期
スギの花粉が飛ぶ春先は、毎年ニュースなどで話題になりやすいものの、実際には植物の種類によって飛散のピークが異なり、症状の出る時期も人によって異なります。
例えば、スギは1月から、ヒノキは3月以降、イネ科植物は5〜6月にかけて花粉が多く飛びます。このように、花粉の飛散時期を知ることが、症状の予防や緩和に繋がります。
原因植物の特徴と飛散時期
| 植物名 | 飛散時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| スギ | 2月~4月 | 代表的な花粉症の原因植物。主に本州・四国・九州の山地に広く分布。 |
| ヒノキ | 3月~4月 | スギと似たアレルゲンを持ち、福島以南の本州や四国・九州に多い。 |
| カモガヤ | 5月~6月 | イネ科の牧草。輸入された外来種で、日本全国に雑草として定着。 |
| オオアワガエリ | 6月~8月 | カモガヤと同様にイネ科の輸入牧草。寒さに強く全国に分布。 |
| ススキ | 9月~10月 | イネ科の多年草で、高さ1〜2mのススキ野原を形成する。 |
| ハンノキ | 1月~4月 | 湿地に多く、全国に分布している落葉樹。 |
| シラカンバ | 3月下旬~6月 | 北海道や本州中部以北に分布。北海道では主要な原因植物。 |
| ブタクサ | 8月~9月 | 秋の代表的な花粉症原因植物。全国に広く分布。 |
| ヨモギ | 9月~10月 | 日本全国に自生。秋に多く飛散する。 |
| カナムグラ | 8月~10月 | 全国に広く分布し、特に関東地方に多く見られる。 |
花粉の飛散量や飛散時期はその年の気象条件によって変化します。また、地域によっても特徴が異なります。例えば、関東や東海地方ではスギ花粉による花粉症が多く見られ、九州地方ではヒノキによる花粉症の割合が高い傾向にあります。
東京都内を例にとると、以下のような飛散スケジュールが目安になります
- 春:スギ(2月〜4月)、ヒノキ(3月〜5月)
- 秋:ブタクサ・ヨモギ(いずれも8月〜10月)
- 春〜秋にかけて:イネ科植物全般(カモガヤ・オオアワガエリ など)
このように、日本全国では年間を通じて何らかの種類の花粉が飛散しており、春や秋に限らず、注意が必要です。
花粉症の主な症状
花粉症は、主に目や鼻の粘膜を中心に、全身に様々な症状を引き起こします。
目の症状
 目がゴロゴロするような異物感や、かゆみ、涙が止まらない、結膜の充血、目やにの増加といった症状が代表的です。
目がゴロゴロするような異物感や、かゆみ、涙が止まらない、結膜の充血、目やにの増加といった症状が代表的です。
鼻の症状
 さらさらとした透明な鼻水が出続けたり、強い鼻づまり、連続するくしゃみなどがよく見られます。
さらさらとした透明な鼻水が出続けたり、強い鼻づまり、連続するくしゃみなどがよく見られます。
皮膚症状
 肌にざらつきやかゆみが出ることもあり、特に顔や首周りに症状が現れることがあります。これらは「花粉症皮膚炎」と呼ばれることもあります。
肌にざらつきやかゆみが出ることもあり、特に顔や首周りに症状が現れることがあります。これらは「花粉症皮膚炎」と呼ばれることもあります。
その他の症状
頭が重い、だるさ、微熱、のどの違和感(かゆみや痛み)、咳など、全身にわたる症状を伴うこともあります。これらは風邪に似ていることもあり、判別が難しい場合もあります。
花粉症と風邪の違い
| 症状 | 花粉症 | 風邪 |
|---|---|---|
| 目 | かゆみ充血涙が止まらない | かゆみは出にくい |
| 鼻 | 透明で水っぽい鼻水強い鼻づまりムズムズ感が続く | 黄色く粘り気のある鼻水が出る長引きにくい |
| のど | かゆみや軽い痛みが出ることがある | 痛みが強く出ることが多い |
| くしゃみ・咳 | くしゃみが1日中頻繁に出る | 咳が主体で、くしゃみはあまり出ない |
花粉症の検査・診断方法
 花粉症の診断にあたって、必ずしも原因となる花粉を特定する必要はありません。というのも、季節によって飛散する花粉の種類はある程度予測が可能であり、治療に使用するお薬はアレルゲンの種類によって大きく変わることがないからです。
花粉症の診断にあたって、必ずしも原因となる花粉を特定する必要はありません。というのも、季節によって飛散する花粉の種類はある程度予測が可能であり、治療に使用するお薬はアレルゲンの種類によって大きく変わることがないからです。
しかしながら、通年でアレルギー症状が出ている場合や、症状が重い場合、あるいは患者様ご本人がご希望される場合には、血液検査によってアレルゲンを特定することができます。スギ、ヒノキ、ブタクサなど、特定の花粉に対するIgE抗体の有無を調べることで、原因となる物質を明らかにします。
「VIEW39」という検査では、代表的なアレルゲン39種類を一度の採血で確認することができ、検査は簡便かつ保険適用(自己負担3割で約5000円)で受けられます。
花粉症の初期療法
初期療法とは、花粉が飛び始める前から抗アレルギー薬などの治療を開始する方法で、症状のピークを和らげたり、発症時期を遅らせたりする効果が期待されます。
治療を開始するタイミング
 治療は、花粉の本格的な飛散が始まる2週間程度前から開始します。
治療は、花粉の本格的な飛散が始まる2週間程度前から開始します。
例えば、東京都内でスギ花粉症の方であれば、花粉の本格的な飛散が始まる2週間ほど前、つまり1月中旬〜下旬を目安に内服薬の服用を開始することが推奨されています。
花粉症の治療方法
症状の強さやタイプに応じて、適切なお薬を選択・処方します。
内服薬(飲み薬)
花粉症の症状が強い場合には、抗ヒスタミン薬を中心とした内服治療が行われます。代表的な薬剤には、ビラノア、デザレックス、ルパフィンなどがあり、症状の程度に応じて処方されます。
必要に応じて、ロイコトリエン受容体拮抗薬(キプレスなど)や、ステロイド薬(セレスタミンなど)を併用するケースもあります。
花粉の飛散量が多くなると、従来使用していたお薬だけでは十分な効果が得られなくなることもあります。そのような場合には、一時的により効果の高いお薬に変更したり、別のお薬を追加して対処することがあります。
なお、お薬の効果や副作用(特に眠気)の感じ方には個人差があります。これまで使用して「よく効いたお薬」や「合わなかったお薬」については、お薬手帳などに記録しておくと、次回以降の診療時に非常に役立ちます。
抗ヒスタミン薬
抗ヒスタミン薬はヒスタミンの作用を抑えることで、鼻水や鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状を軽減します。以前の抗ヒスタミン薬には眠気の副作用が強く出やすい傾向がありましたが、現在は副作用を抑えた「第2世代抗ヒスタミン薬」が主流となっています。代表的なお薬として、ビラノア、デザレックス、ルパフィンなどが挙げられます。
ロイコトリエン受容体拮抗薬
ロイコトリエンはアレルギー反応の中で生成される物質の1つで、鼻の粘膜に炎症や腫れを引き起こし、鼻づまりの原因となります。
ロイコトリエン受容体拮抗薬はロイコトリエンの作用をブロックすることで、粘膜の腫れを抑え、鼻の通りを改善する効果があります。特に鼻づまりが主症状として強く現れる場合に効果的であり、よく使用されるお薬には、キプレス、オノン、シングレアなどが挙げられます。
点眼薬(目薬)
目のかゆみや充血が強い場合は、ステロイドや抗ヒスタミン成分を含む点眼薬を使用します。
コンタクトレンズの上からは使用できないため、レンズは外してから点眼し、一定時間を空けて再装着してください。
点鼻薬(鼻スプレー)
鼻水や鼻づまりの症状が強い場合は、血管収縮薬やステロイドの点鼻薬を使用することがあります。
薬剤が粘膜にしっかり届くよう、使用前には必ず鼻をかんでからスプレーしてください。
減感作療法(アレルゲン免疫療法)
減感作療法(アレルゲン免疫療法)は、アレルギーの原因物質を少量ずつ体内に入れて、過敏性を低下させる治療法です。アレルギー体質そのものを改善する「根本的治療」として期待されているのがアレルゲン免疫療法です。花粉のアレルゲンを少量ずつ体に取り入れ、徐々に慣らしていくことで、症状を起こさない体質へ導く治療です。
副作用は少なく、長期的な改善を目指す方法として注目されています。デメリットとしては、治療途中にアナフィラキシ―を生じる危険性があり、注射による痛みともに、通院による患者の負担が大きいという点があります。
減感作療法(アレルゲン免疫療法)には、注射によるものと舌下薬(口から投与する方法)がありますが、当院では口からを基本とします。
舌下薬による減感作療法(舌下免疫療法)は、アレルギーの原因物質を含んだ医療用の舌下薬(錠剤もしくは液剤)を使用する治療法です。舌下に治療薬を投与して1~2分間待った後に飲み込みます。1回目の舌下投与はアレルギー反応の評価やアナフィラキシーの有無の評価の為が必要な為、医療機関で行いますが、通常それ以降は毎日自宅で行なえます。注射による減感作療法に比べ、注射による痛みがなく、通院回数が少なくて済むメリットがあります。
舌下免疫療法では、初年度より2年目、2年目より3年目以降で効果が高くなるので、3~5年間続けることが望ましいと考えられています。完全に治る(根治)率は10~20%程度で、とても改善が20~30%、改善が20~30%となり、70~80%の患者さんで有効となります。従来の注射法より、治療成績がより勝るという報告はありませんが、同等に効いたという報告があります。しかし、今までの注射の方法と比較し、重い副反応が少なく安全と考えられています。
スギ花粉症に対する舌下免疫療法は、既存の抗ヒスタミン薬のように、くしゃみ・鼻水・鼻つまりなどの花粉症症状自体を抑えるものではなく、あらかじめ、花粉飛散前に治療を開始し、症状を出にくくするものです。従って、治療の開始は花粉症の症状が出てからでなく、数ヶ月以上前から行う予防的なものとなります。スギ花粉の本格飛散が始まる3ヶ月以上前から治療を開始すると効果的なので、6月から11月に治療を開始するのが望ましと考えられます。
毎年、花粉症に時期に症状がひどく、たくさんの薬を服用しなければならなく、それでも症状に悩まされている方、受験や就職などの大切な時期にスギ花粉症で悩まされて困っている方、今後の長い人生でこれからもずっと毎年スギ花粉症で悩まされることが憂鬱・不安な方などは、この方法が適していると考えられます。
どの診療科を受診すれば良いか?
花粉症の診療は、当院のほか、耳鼻咽喉科(耳鼻科)、眼科、で対応可能です。耳鼻科や内科でも点眼薬を処方できます。
花粉症の予防方法
花粉症の症状を抑えるには、まず花粉を体内に取り込まないことが重要です。外出時にはマスクの着用や花粉対策用のゴーグル型メガネを使用することで、目や鼻、口への花粉の侵入を防げます。
また、帰宅時には玄関先で衣類に付着した花粉をブラシなどで払い落とすことも効果的です。さらに、外に干した布団や洗濯物は、取り込む前にしっかり叩いて花粉を落とすなど、家庭内への花粉の持ち込みを防ぐ工夫が大切です。
花粉症治療時の注意点
現在は眠気の少ない第2世代抗ヒスタミン薬が主流ですが、お薬による眠気の感じ方には個人差があります。
服薬によって仕事や車の運転に支障が出ないか不安な方は、診察時に遠慮なくご相談ください。症状や生活スタイルに応じた処方を検討いたします。
セルフケアとしての市販薬活用
 花粉症には、市販薬でも一定の効果が見込まれます。なかでも第2世代の抗ヒスタミン薬は、眠気が少なく日常生活に支障をきたしにくいため、多くの薬局で取り扱われています。
花粉症には、市販薬でも一定の効果が見込まれます。なかでも第2世代の抗ヒスタミン薬は、眠気が少なく日常生活に支障をきたしにくいため、多くの薬局で取り扱われています。
また、点鼻薬や点眼薬といった局所用の薬も市販されており、比較的手軽に入手できます。ただし、現在服用しているお薬との相互作用や症状との相性もあるため、購入の際は薬剤師が常駐している薬局で相談のうえ選ぶことをお勧めします。
花粉症でお悩みの方は
当院までご相談ください
 花粉症は、スギやヒノキなどの花粉に対するアレルギー反応によって起こる疾患で、鼻水・鼻づまり・くしゃみといった鼻の症状や、目のかゆみ・充血といった目の症状を引き起こします。
花粉症は、スギやヒノキなどの花粉に対するアレルギー反応によって起こる疾患で、鼻水・鼻づまり・くしゃみといった鼻の症状や、目のかゆみ・充血といった目の症状を引き起こします。
治療の基本は薬物療法であり、抗ヒスタミン薬・ロイコトリエン受容体拮抗薬・点鼻薬・点眼薬などを症状に応じて組み合わせて使用します。近年では、アレルゲン免疫療法が根本治療として注目されており、これまでお薬だけでは効果が不十分だった方にも改善が期待されています。
当院では、必要に応じて血液検査でアレルゲンを特定し、初期療法・飲み薬・点鼻薬・点眼薬などを患者様ごとに適した形でご提案しています。また、眠気の少ないお薬や、費用負担を抑えられるジェネリック医薬品の処方にも対応しております。
花粉症の症状やお薬の効き方には個人差があるため、以前にあまり効果がなかったお薬や、ご希望のお薬がある場合には、お薬手帳やメモで薬剤名をお知らせください。市販薬や他院での治療で改善しなかった方も、お気軽にご相談ください。













