消化器内科について
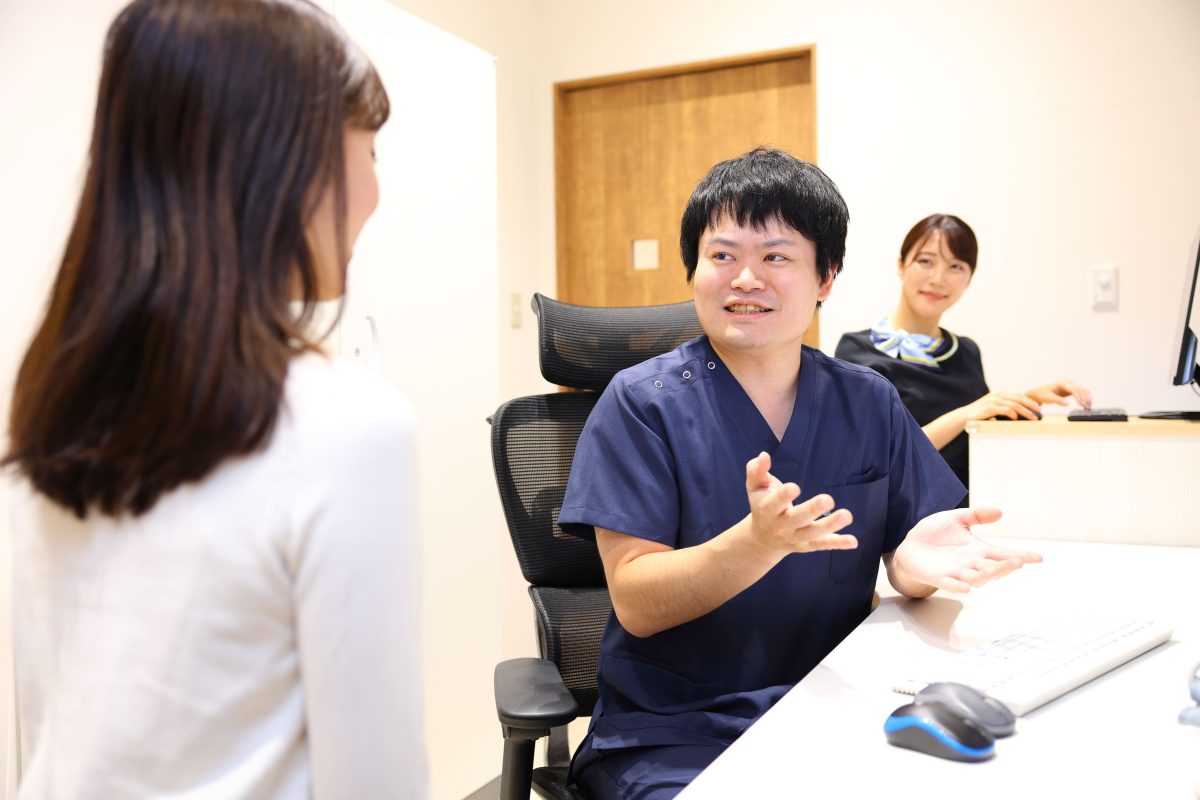 消化器は大きく2つの領域に分けられます。
消化器は大きく2つの領域に分けられます。
1つは、食べ物を口から摂取して排泄に至るまでの通り道である「消化管」で、栄養や水分の吸収・消化といった重要な役割を担っています。もう1つは、肝臓・胆のう・膵臓といった臓器群で、消化液の分泌や代謝、ホルモンの調整など体内環境の維持に深く関わっています。
これらのいずれかに異常が生じると、腹痛や下痢といった腸の不調だけでなく、糖尿病、肝硬変、さらには消化器がんなど、様々な疾患が引き起こされる可能性があります。これらに対して、主に薬物療法を中心とした治療を行うのが消化器内科です。
以下のような症状が見られる場合、消化器系に何らかの異常が起きている可能性があります。早期に受診することで重篤な疾患の早期発見に繋がることもありますので、気になる症状があればお早めにご相談ください。
消化器に関連する主な症状
消化器に関連する主な疾患
急性胃炎
 急性胃炎は、胃の粘膜に急激な炎症が起こる病気で、胃の不快感、強い腹痛、吐き気などの症状を伴います。症状が悪化すると、出血によって血便や吐血が見られることもあります。
急性胃炎は、胃の粘膜に急激な炎症が起こる病気で、胃の不快感、強い腹痛、吐き気などの症状を伴います。症状が悪化すると、出血によって血便や吐血が見られることもあります。
広範囲にびらん(ただれ)が生じる「急性胃粘膜病変」は、ストレス、香辛料などの刺激物の過剰摂取、過度な飲酒、薬剤(解熱鎮痛薬や抗菌薬)などが引き金となります。
現在では胃カメラ検査によって胃粘膜の状態を詳細に確認できるようになり、正確な診断と治療が可能となっています。
慢性胃炎・萎縮性胃炎
 慢性胃炎は、長期間にわたって胃の粘膜に炎症が続く状態であり、胃液や胃酸を分泌する組織が減少すると、粘膜が萎縮する「萎縮性胃炎」に進行します。
慢性胃炎は、長期間にわたって胃の粘膜に炎症が続く状態であり、胃液や胃酸を分泌する組織が減少すると、粘膜が萎縮する「萎縮性胃炎」に進行します。
この状態が長く続くと、胃がん発症のリスクが高まることが知られています。特にピロリ菌の除菌治療を行うことで、胃がんのリスク低下が期待されます。
慢性胃炎と診断された方には、胃カメラ検査を定期的に受けましょう。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
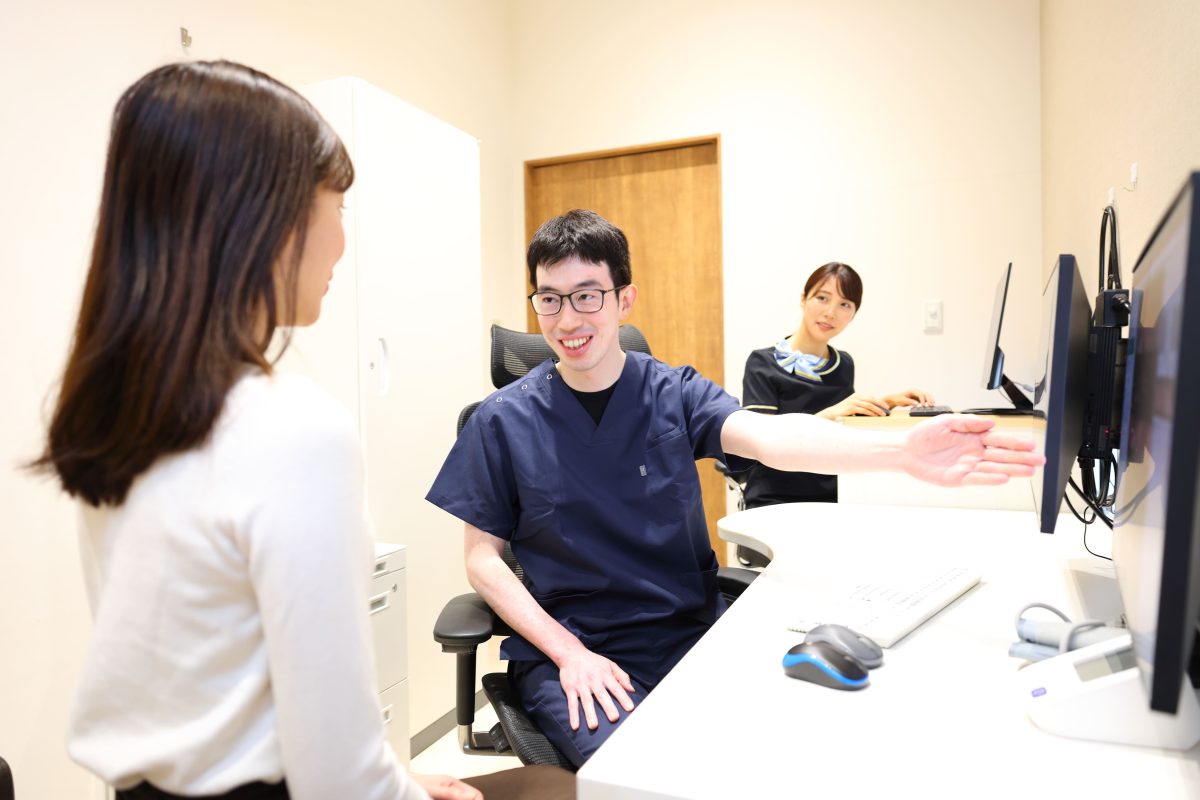 胃潰瘍および十二指腸潰瘍は、胃酸や消化酵素が自らの粘膜を深く傷つけることで発症します。
胃潰瘍および十二指腸潰瘍は、胃酸や消化酵素が自らの粘膜を深く傷つけることで発症します。
主な原因はピロリ菌感染で、その他にもストレスや薬剤(NSAIDsなど)が関係することがあります。
発症すると、みぞおちや背中の痛み、胃の張り、吐き気、胸焼けなどの症状が現れ、進行すると吐血や下血を伴うこともあります。
潰瘍は40代以降の中高年に多く見られますが、ピロリ菌に感染している若年層でも発症することがあります。
胃がん
 胃がんは日本において比較的発症頻度の高いがんであり、特に萎縮性胃炎のある方に多く見られます。
胃がんは日本において比較的発症頻度の高いがんであり、特に萎縮性胃炎のある方に多く見られます。
ピロリ菌感染が主な原因とされているほか、食生活の乱れ(塩分の過剰摂取など)、喫煙、栄養バランスの偏りなども発症リスクを高めます。
早期発見のためには胃カメラによる定期的な検査が重要で、近年では内視鏡技術の進歩により、早期がんの診断や治療がより容易かつ精度高く行えるようになっています。
ヘリコバクター・ピロリ感染症
 ピロリ菌は多くの場合、幼少期に口から体内に入り、胃の粘膜に定着して炎症を引き起こします。感染を放置すると、萎縮性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんへと進行するリスクがあります。
ピロリ菌は多くの場合、幼少期に口から体内に入り、胃の粘膜に定着して炎症を引き起こします。感染を放置すると、萎縮性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんへと進行するリスクがあります。
薬物療法により除菌治療を行うことで、これらの疾患の予防・再発防止に繋がります。検査でピロリ菌陽性と診断された場合は、早めの治療が重要です。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流することで、食道の粘膜に炎症が生じる疾患です。
症状としては、胸焼け、のどの違和感・ヒリヒリ感、酸っぱいものが上がってくる感覚(呑酸)などがあります。
胃酸の分泌過多や、胃酸の逆流を防ぐ機能の低下が原因となり、加齢、過食、肥満、アルコールの常飲、姿勢の悪さ、食道裂孔ヘルニアなどが関係します。そのため、生活習慣の見直しと薬物療法によって改善が期待できます。
食道がん
 食道がんの主なリスク因子には、喫煙と過度な飲酒が挙げられます。初期の段階ではほとんど自覚症状がありませんが、進行すると、のどのつかえ感、胸焼け、胸痛などの症状が現れるようになります。
食道がんの主なリスク因子には、喫煙と過度な飲酒が挙げられます。初期の段階ではほとんど自覚症状がありませんが、進行すると、のどのつかえ感、胸焼け、胸痛などの症状が現れるようになります。
早期に発見された場合は、内視鏡による低侵襲な治療で根治が可能なケースも増えています。喫煙や飲酒の習慣がある方、バレット食道と診断されたことのある方は、定期的に胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
肝機能障害
肝機能障害とは、肝臓の細胞が炎症などにより傷つき、その結果として肝細胞内の酵素(AST、ALTなど)が血液中に漏れ出すことで検出される病態です。
原因は多岐にわたり、B型・C型などのウイルス性肝炎、脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、アルコールの過剰摂取、薬剤による副作用、自己免疫性肝炎などが代表的です。
血液検査で肝機能異常を指摘された場合は、放置せず早めに消化器内科を受診してください。特に脂肪肝やアルコール性肝障害が疑われる場合には、食事や運動といった生活習慣の見直しによって進行を食い止めることが可能です。
脂肪肝
 脂肪肝は、肝臓に過剰な中性脂肪が蓄積された状態で、肝細胞の30%以上に脂肪が沈着していると診断されます。
脂肪肝は、肝臓に過剰な中性脂肪が蓄積された状態で、肝細胞の30%以上に脂肪が沈着していると診断されます。
その多くは、糖質・脂質の過剰摂取や運動不足などによって引き起こされ、肥満やメタボリックシンドロームと合併することが多く見られます。
放置すると脂肪肝は単なる代謝異常に留まらず、慢性の炎症を引き起こし、やがて肝炎や肝硬変へ進行する可能性があります。さらに糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病を招き、動脈硬化を進行させる危険性も高まります。
脂肪肝は見過ごされがちですが、放置すれば健康に深刻な影響を及ぼすため、早期の対処と継続的な管理が非常に重要です。
慢性肝炎・肝硬変
肝臓に6カ月以上慢性的な炎症が続いている状態を「慢性肝炎」と呼びます。主な原因はB型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスによるものとアルコールが挙げられます。ウイルス性の慢性肝炎は、日本においては約70~80%がC型肝炎ウイルス、15~20%がB型肝炎ウイルスとされています。また、長期間の過度の飲酒によりアルコール性の慢性肝炎を来すことがあります。
治療法は原因によって異なるため、的確な診断とそれに応じた治療が必要です。
慢性肝炎が長期間続くと「肝硬変」へと進行することがあります。これは、肝臓内に線維組織が増え、柔らかかった肝臓が硬くゴツゴツとした組織に変化し、機能が低下していく状態です。
進行すると肝不全や肝がんなどの合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
肝臓がん
肝臓がん(肝細胞がん)は、主にウイルス性肝炎(B型・C型)やアルコール性肝炎、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)などが原因で発症します。なかでも約90%はウイルス性肝炎に起因するとされています。
ウイルス感染が長期間続くと、肝細胞の破壊と再生が繰り返される過程で「がん遺伝子の活性化」や「がん抑制遺伝子の機能低下」などの遺伝子異常が蓄積し、発がんリスクが高まります。
また、大量の飲酒も肝細胞にダメージを与え、同様に遺伝子異常を引き起こす要因となります。アルコールを摂取しない方でも、脂肪肝から炎症が進行することで肝がんを発症することがあります。
現在ではウイルス性肝炎の治療が進歩したことで、ウイルス由来の肝がんは減少傾向にありますが、NAFLDに関連する肝臓がんは増え続けています。
胆石(胆のう結石症)・胆のう炎
胆のう内に形成される結石を「胆石(胆のう結石)」と呼びます。多くの場合は無症状であり、健康診断などで偶然発見されることも少なくありません。
ただし、胆石が胆のうの粘膜を刺激して炎症を引き起こすと「胆のう炎」となり、みぞおちから右側の肋骨下部にかけての激しい痛みが現れることがあります。この痛みは背中や右肩にまで放散することもあります。
腹痛などの症状が出ている場合は、早めに消化器内科の受診をお勧めします。
急性膵炎・慢性膵炎
膵臓は、食べ物の消化を助けるためにアミラーゼ(炭水化物分解)、トリプシン(タンパク質分解)、リパーゼ(脂質分解)などの消化酵素を分泌しています。これらの酵素は、膵臓内では不活性の状態で存在しており、自らを消化しないよう制御されています。
しかし、過度の飲酒や胆石などが原因で酵素が膵臓内で活性化されると、膵臓自身を消化してしまう「自己融解」が起こります。これが「急性膵炎」です。主な症状は腹痛、背中の痛み、発熱などです。
一方、「慢性膵炎」は膵臓に繰り返し炎症が生じ、組織が線維化していく病気です。主な原因はアルコールの常用や喫煙で、膵臓の機能が徐々に低下していきます。進行すると、膵石が形成されたり、糖尿病、脂肪便(下痢)、黄疸などの症状が現れることがあります。
初期のうちから定期的な検査と生活習慣の見直しにより、進行の抑制が期待できます。
膵臓がん
膵臓がんは、明確な初期症状が現れにくく、早期発見が難しい疾患です。
初期には、食欲の低下、体重減少、腹部の違和感など、他の病気でもよく見られるような漠然とした症状が中心です。進行すると、胃の不快感や腹痛、背中や腰の痛み、黄疸などの症状が起こります。
発症の原因はまだ完全には解明されていませんが、喫煙、糖尿病、慢性膵炎、家族歴などが関与していると言われています。
これらのリスク因子がある方は、定期的な検査(腹部超音波検査(エコー)、MRI検査)を受けて早期発見に努めることが大切です。
※腹部超音波検査だけでは、膵臓のすべてを観察することは難しく、必要に応じてMRI検査を受けることが重要です。
便秘症
 便秘症にはいくつかの分類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。代表的なものは以下の通りです。
便秘症にはいくつかの分類があり、それぞれ原因や対処法が異なります。代表的なものは以下の通りです。
- 機能性便秘:腸の動きや排便の機能に異常が生じているタイプで、最も一般的です。
- 器質性便秘:大腸がん、術後の癒着、炎症性腸疾患潰瘍性大腸炎(UC)、クローン病)など、腸に器質的な異常がある場合に起こります。
- 症候性便秘:糖尿病や甲状腺機能低下症など、全身疾患の症状として見られます。
- 薬剤性便秘:服用しているお薬の副作用によって引き起こされます。
便秘は単なる生活習慣の問題ではなく、重大な病気が隠れていることもあります。症状が続く場合は、医療機関で原因を調べ、適切な治療を受けましょう。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、便秘や下痢といった排便異常が数カ月以上持続し、腹痛やお腹の張りなどの症状を伴うにもかかわらず、検査では特に異常が見つからない状態を指します。
原因は明確になっていませんが、器質的な異常、胃がん大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎(UC)、クローン病)がないことを、適切な検査(胃カメラ検査・大腸カメラ検査・血液検査)などで除外することが重要です。
ストレスや自律神経の乱れなど、心理的な要因が深く関係していると考えられています。症状に心当たりのある方は、一度ご相談ください。
大腸がん
 大腸がんの多くは、大腸ポリープ(腺腫)が徐々にがん化することで発症します。その他、大腸粘膜の慢性的な炎症や、粘膜から直接がんが発生する場合もあります。 近年では、食生活の欧米化や高齢化が発症リスクを高める要因とされています。
大腸がんの多くは、大腸ポリープ(腺腫)が徐々にがん化することで発症します。その他、大腸粘膜の慢性的な炎症や、粘膜から直接がんが発生する場合もあります。 近年では、食生活の欧米化や高齢化が発症リスクを高める要因とされています。
初期には自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。
早期発見には定期的な大腸カメラ検査が極めて有効です。
また、大腸ポリープが見つかった場合は、切除することで将来的ながんのリスクを大幅に軽減できます。家族に大腸がんがいる方や、乳がんや胃がんなど他部位にがんが見つかった方、腹部症状や便通障害のある方、血便がある方などは必ず検査(大腸カメラ検査)を受けるようにしましょう。













