以下のような症状がある方はご相談ください
- 排便が3日以上ない
- 強い腹痛を伴う
- 便が硬い
- 便秘に加えて吐き気がある
- 市販の下剤を使っても効果がない
- 排便時に出血が見られる
- 肛門が切れて痛みや出血がある
- 排便後もスッキリしない、残便感が続く
便秘について
 便秘とは、排便が3日以上ない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態を指します。排便の回数が正常範囲内であっても、便が硬くて強くいきまないと出ない、あるいは排便後にもスッキリしないと感じる場合も、便秘とみなされます。
便秘とは、排便が3日以上ない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態を指します。排便の回数が正常範囲内であっても、便が硬くて強くいきまないと出ない、あるいは排便後にもスッキリしないと感じる場合も、便秘とみなされます。
便秘は年齢や性別を問わず誰にでも起こり得る身近な症状ですが、慢性化している方も少なくなく、「いつものこと」として放置されがちです。
しかし、放っておくことで腸内環境に悪影響を及ぼし、腹部の膨満感や食欲低下、肌荒れなど、様々な不調の原因になることがあります。
違和感を覚えたら、早めに医療機関で相談することをお勧めします。
便秘の原因・種類
便秘の原因は様々で、主に「機能性便秘」と「器質性便秘」の2つに大別されます。機能性便秘はさらに以下の3つのタイプに分類され、それぞれ異なる背景があります。
弛緩性便秘(運動不足や過度なダイエットが原因)
腸の動き(蠕動運動)が弱まり、便が大腸内に長く留まることで水分が吸収されて硬くなり、排便が困難になります。
このタイプは便秘の中でも最も多く見られ、特に高齢者や女性に多い傾向があります。
主な症状には、腹部の張り感、残便感、食欲不振、肩こり、肌荒れ、イライラなどが挙げられます。
痙攣性便秘(ストレスや自律神経の乱れが原因)
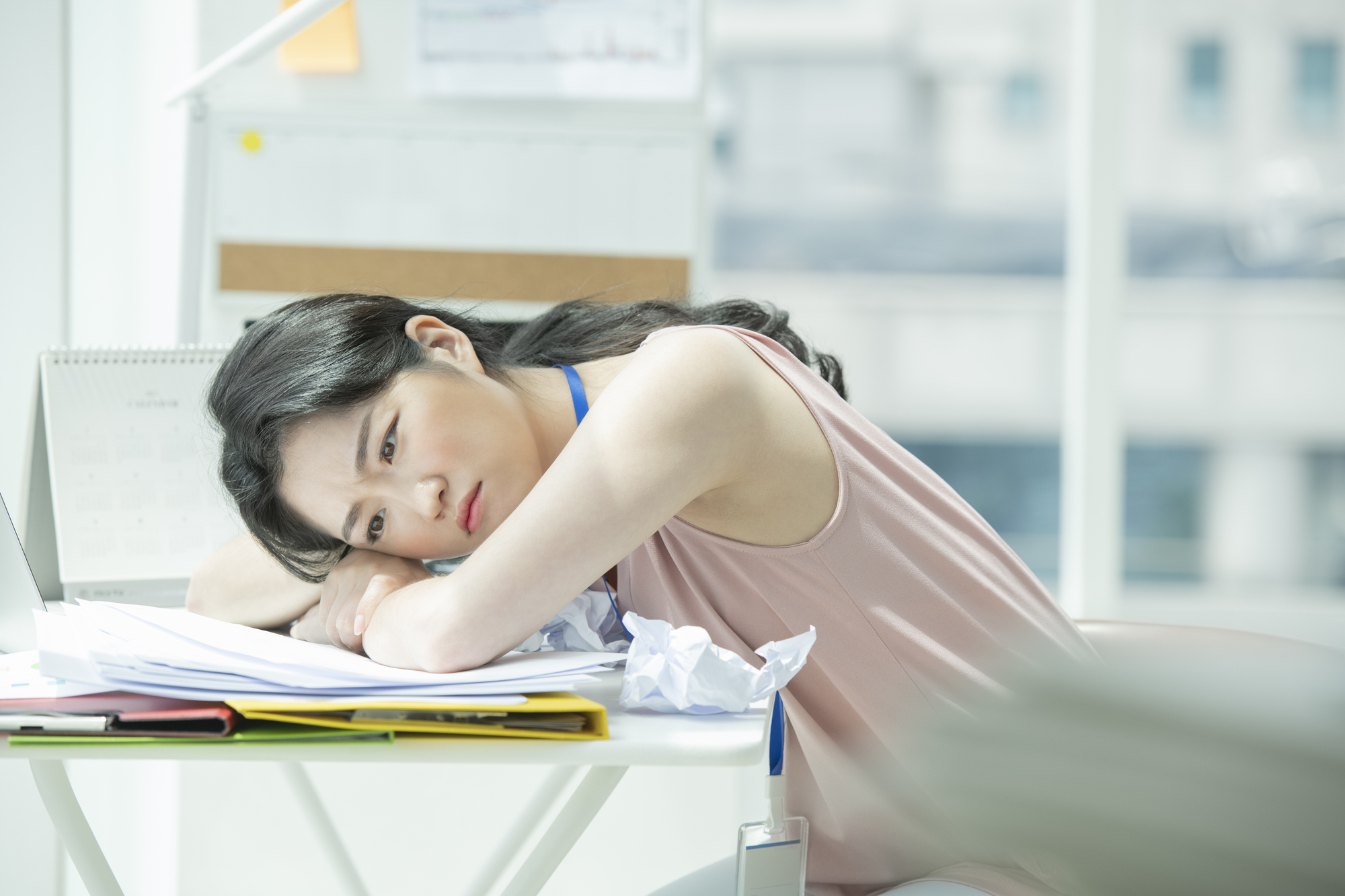 精神的な緊張や生活環境の変化、過敏性腸症候群などが誘因となり、腸が過度に収縮して便の通過が不規則になります。
精神的な緊張や生活環境の変化、過敏性腸症候群などが誘因となり、腸が過度に収縮して便の通過が不規則になります。
ウサギのフンのようなコロコロとした便が特徴です。
食後の腹痛、残便感、便秘と下痢を交互に繰り返すなどの症状が現れます。
このタイプでは、原因となるストレスの除去が改善の鍵になります。
直腸性便秘(排便反射が起こらないことが原因)
直腸に便が届いても排便の反射が起こらず、便がそのまま停滞してしまいます。
排便を我慢する習慣がある方や、痔による排便の痛みを避けたい方、高齢者、寝たきりの方によく見られます。
器質性便秘(腸の構造的な異常が原因)
大腸がんやイレウス(腸閉塞)、過去の手術による腸の癒着など、腸の通過障害が原因で起こる便秘です。このタイプは下剤の使用が禁忌であり、使用すると腸管穿孔などの重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。
- 大腸がん
- 骨盤内腫瘍・腫瘤
- 子宮筋腫
便秘が原因となる主な疾患
- 痔
- 直腸脱
- 裂肛
- 憩室性疾患
- 宿便
痔・直腸脱
排便時に強くいきむことで、肛門周囲の血流が悪化し、痔(いぼ痔・切れ痔など)を引き起こすことがあります。稀に、直腸の一部が肛門の外に脱出する直腸脱を生じるケースもあります。
痔になると排便時の痛みが強くなり、排便自体を避けるようになって便秘がさらに悪化するなど、悪循環に陥る恐れがあります。そのため、早期の対策が重要です。
大腸憩室症
大腸憩室症とは、大腸の壁に小さな袋状のへこみ(憩室)ができる状態を指します。通常は無症状ですが、稀に憩室内に細菌感染が生じると憩室炎を起こし、腹痛や発熱を伴います。抗生剤で加療し、重症の場合、入院したりします。
憩室の血管が破れることで出血が起こることもあり憩室出血といいます。
憩室出血の治療としては、血が止まらない際には、まず内視鏡による止血術が行われますが、効果が不十分な場合には動脈塞栓術や大腸切除術が検討されることもあります。いずれも入院での加療となります。
宿便
宿便とは、便が直腸または下行結腸に長時間留まり、硬く固まってしまう状態です。このため新たな便の通過が妨げられ、排便困難を引き起こします。
典型的な症状には、痙攣性の腹痛や直腸の圧迫感があり、排便してもすっきりしない感覚が続きます。
ときに、水っぽい便や粘液が漏れ出し、下痢と誤認されることもあります。
宿便は、特に活動量が少ない高齢者や妊娠中の女性、バリウム検査後などで浣腸を使用した方に発生することが多いです。
便秘の検査・診断方法
 便秘の診断では、まず医師による問診と診察が行われます。
便秘の診断では、まず医師による問診と診察が行われます。
便の性状や排便頻度、腹痛の有無、生活習慣などを確認したうえで、必要に応じて検査を進めます。
検査では、必要に応じて腹部レントゲン検査によって腸内のガスの溜まり具合や便の停滞を確認します。
また、大腸カメラ検査を通じて、大腸がんなどの器質的疾患が隠れていないかどうかを詳しく調べます。
腸の捻じれや狭窄が疑われる場合にも、画像検査によって正確に把握し、検査結果に基づいた治療方針を立てていきます。
便秘の治療方法
治療の基本は、生活習慣の見直しにあります。食事・運動・排便リズム・ストレス管理など、日々の行動を整えることが、便秘の改善に直結します。
食事を規則正しく摂る
 1日3食を規則正しく摂ることが大切です。
1日3食を規則正しく摂ることが大切です。
特に朝食は、腸の動きを活性化させ、自然な排便を促すため、毎日欠かさず摂りましょう。
食物繊維や水分をしっかり摂る
 食物繊維には腸の蠕動運動を活発にし、便通を促す作用があります。
食物繊維には腸の蠕動運動を活発にし、便通を促す作用があります。
海藻、寒天、穀類、いも類、豆類、果物(キウイ)、ヨーグルトなどを日々の食事に積極的に取り入れましょう。
また、水分が不足すると便が硬くなり、腸内で停滞しやすくなります。
朝起きたら、冷たい水や牛乳を一杯飲むことで、腸が刺激されて排便が促されやすくなります。
適度な運動を取り入れる
 運動不足は、特に弛緩性便秘の大きな原因となります。腹筋などを中心とした適度な運動は、排便をサポートする筋力の維持に繋がります。
運動不足は、特に弛緩性便秘の大きな原因となります。腹筋などを中心とした適度な運動は、排便をサポートする筋力の維持に繋がります。
運動が難しい方でも、お腹のマッサージを日課にすることで、腸の動きを助ける効果が期待できます。
便秘にお悩みの方は
当院までご相談ください
市販薬として入手可能な刺激性下剤や浸透圧性下剤は、一定の効果がある反面、刺激性下剤は依存性や耐性の問題があるため、継続的な使用には注意が必要です。
便秘の種類によって適切な薬剤が異なるため、自己判断によるお薬の使用では効果が出にくいこともあります。
消化器専門の医療機関では、これまでとは作用の異なる新しいタイプの薬剤を処方することも可能で、耐性がつきにくいのが特長です。
便秘が慢性化している方、合併症を伴っている方、市販薬や従来の治療で効果が得られなかった方は、一度当院までご相談ください。













