慢性肝障害について
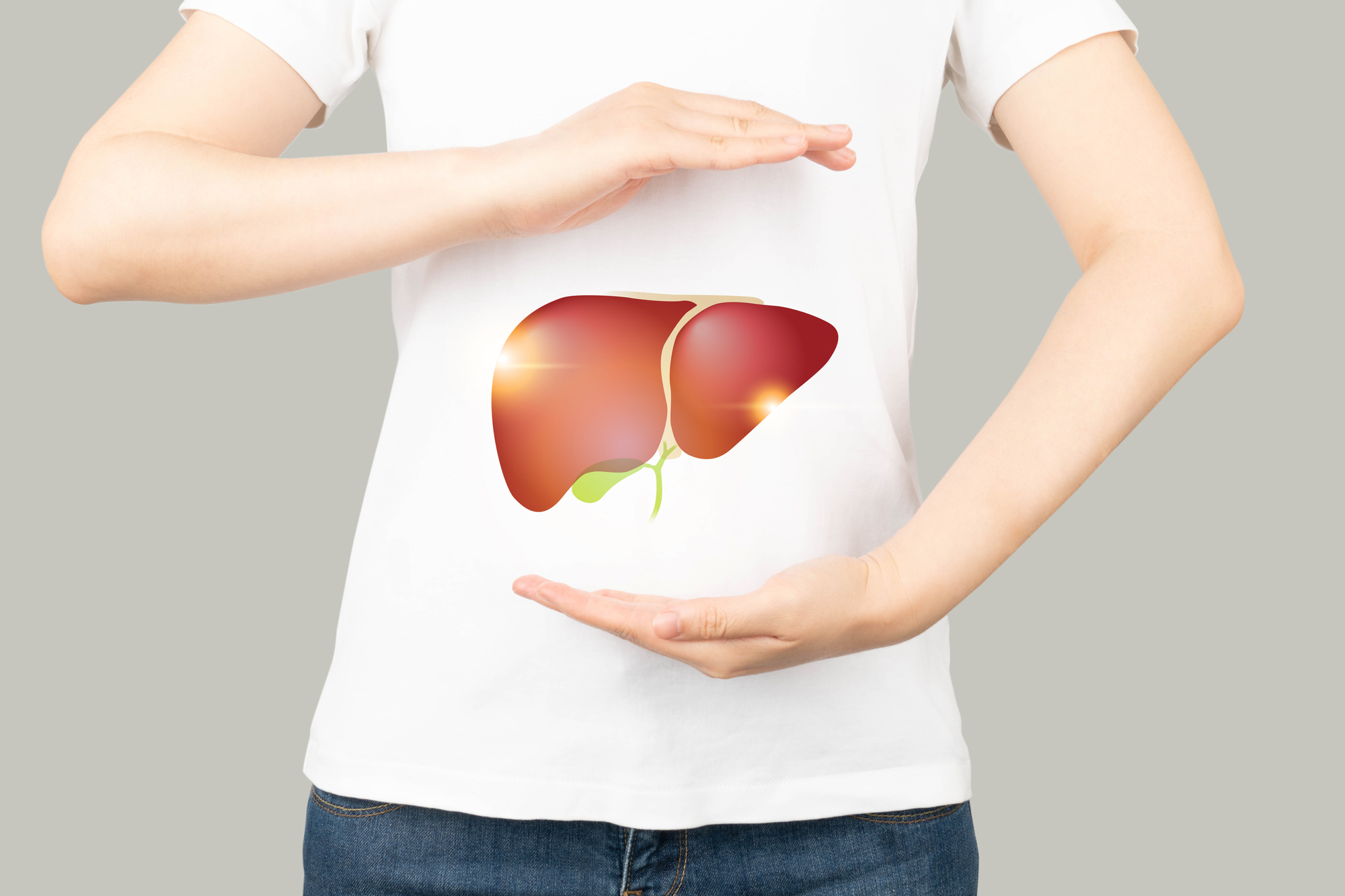 慢性肝障害とは、6カ月以上にわたって肝臓に炎症や障害が続いている状態を指します。
慢性肝障害とは、6カ月以上にわたって肝臓に炎症や障害が続いている状態を指します。
「肝臓の数値が高い」「肝機能の数値異常を指摘された」といった理由で受診される方が多く見られます。
この段階では、多くの方が自覚症状がないか、あっても倦怠感・疲れやすさ・食欲低下など軽い症状に留まることが一般的です。
代表的な原因にはウイルス性肝炎(B型・C型)が挙げられます。
その他、脂肪肝の放置による進行性肝障害、自己免疫性肝炎、原発性硬化性胆管炎なども原因となります。
B型肝炎
 HBV(B型肝炎ウイルス)の持続感染によって発症します。感染経路は母子感染や血液・体液を介した感染が主です。
HBV(B型肝炎ウイルス)の持続感染によって発症します。感染経路は母子感染や血液・体液を介した感染が主です。
治療法としては、ウイルスの増殖を抑えるためにガイドラインに基づき核酸アナログ製剤やインターフェロン療法などが用いられます。治療を受けずにいると、肝硬変や肝がんへ移行する恐れもあります。
C型肝炎
HCV(C型肝炎ウイルス)の持続感染が原因で、主な感染経路は血液感染です。
医学の進歩により、飲み薬を2-3ヶ月飲むだけでほとんどの例でC型肝炎を治せるようになりました。
C型肝炎ウイルスはB型肝炎ウイルスと違って、完全に排除できます。そのため、ウイルスを追い出したり肝機能の悪化を防いだりする治療を行います。
治療法は主に、インターフェロンフリー療法という内服薬による治療でウイルスを体外から排除することが可能となっています。
慢性肝炎を治療せず放置した場合、10〜20年かけて肝硬変へ進行するケースが多く報告されています。
肝硬変に至ると、肝臓がんの発症リスクが大きく高まります。
肝硬変
肝細胞が長年にわたり炎症や破壊を繰り返すことで、肝臓の組織が線維化し硬くなってしまった状態を肝硬変と呼びます。
この状態にまで進行した肝臓は、元の正常な機能に回復することはできず、治療は以下が主な目的となります。
- これ以上肝機能を悪化させないようにする
- 機能が低下した肝臓を補う治療を行う
- 合併症(腹水・静脈瘤出血など)への対処
そのため、肝硬変へ進行する前に早期発見・治療を行うことが極めて重要です。
慢性肝障害の検査・診断方法
| 血液検査 | 肝機能や肝炎ウイルスの有無を調べます。 |
|---|---|
| 腹部超音波検査(腹部エコー検査) | 肝臓の形状や腫大、脂肪沈着、腫瘍の有無などを確認します。 |
| CT・MRI検査 | 肝臓の形状や腫大、脂肪沈着、特に、腹部超音波検査では観察が難しい背側の腫瘍の有無などを確認します。 |
| 肝生検 | 専用の針で肝臓の組織を採取し、顕微鏡で状態を詳しく調べます。 ※当院では施行できませんが、必要に応じて専門医療機関をご紹介いたします。 |
肝硬度測定
フィブロスキャンという専用の装置を用いた検査では、痛みを伴わずに短時間で肝臓の硬さを数値化することができます。
この検査は肝硬変に進行しているかどうかの目安となり、肝生検を行わない代替手段として有効です。また、肝疾患の経過観察にも広く活用されています。













